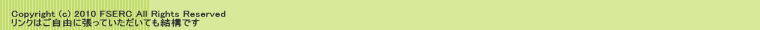目的
目標
内容
日本の自然環境は人間活動により大きく改変され、深刻な環境問題に直面しています。1000万ha(国土の27%)を占める人工林のうち65%では間伐が遅れています。こうした放置人工林では表土がむき出しとなって流出し、森林のみならず河川、河口、浅海域の生態系の荒廃の原因になります。
また、人工林や里山の森林資源をエネルギーとして利用しなくなったことで、農山村の荒廃が進んでいます。
「森里海連環学による地域循環木文化社会創出事業」(木文化プロジェクト)は、「森里海連環学」(もりさとうみれんかんがく)を基礎として、大学と地域との連携融合による教育研究を行い、森川里海のつながりを再生し、自然環境と共生する地域循環木文化社会の創生を目指しています。本プロジェクトは、文部科学省概算要求(連携融合事業)による研究プロジェクト(2009年度~2013年度)です。
① 森林の管理施業による森林および流域環境への影響を解析し、森と水域(川・海)の連環の様相を明らかにし、健全な生態系の再生に最適な森林管理方法を検討します。
② 間伐材をはじめとする木質資源の利用過程を追跡し、地域経済への貢献と森林資源の量と質の向上を両立できる新たな資源利用を検討します。
③ 森林管理をめぐる一連の活動が、流域に暮らす人々の意識に及ぼす影響について解析します。
京都府由良川流域と高知県仁淀川流域をモデルとして、人工林の大規模な間伐操作実験を行い、森から海に至る生態系や生物の応答を解析します。水質、土壌、植物、動物、水生生物を調査しています。
間伐材の利用方法を検討し、市場流通の追跡調査を行います。
アンケート調査等から、森林や木材等の森林資源の活用に対する意識を明らかにします。
ページトップへ
|