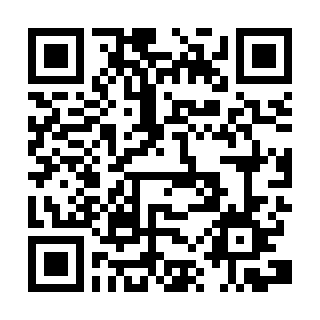2025年公開森林実習Ⅰは、2025年9月3日(水)~5日(金)の日程で開催しました。京都先端科学大学、近畿大学、筑波大学、宮崎大学、明治大学から計9名の学生が参加しました。
実習の目的は、京都における里山と奥山の両方において、森林の歴史や現在の状況(ナラ枯れ・マツ枯れ・シカによる食害・人工林の管理)を体験学習し、森林をめぐる環境問題に対し、科学的な知識や研究手法を習得することです。本拠点事業では特に、地域の人々との交流や活動の体験を通じて、人間社会と森林の関係について考察し、持続的な人と森との関係のあり方を多面的に考えられるようになることを実習の特色として掲げています。
初日は京都市の里山について、上賀茂試験地で講義と実習を行いました。上賀茂試験地では、都市近郊林の自然植生とナラ枯れ・マツ枯れ被害、マツ類を中心とする外国産樹種とその特徴の解説に、受講生は興味深く耳を傾けていました。次に、イオン環境財団と協働で行っている「里山おーぷんらぼ」という、市民参加型の里山活動について、説明と活動場所の見学がありました。さらに、上賀茂試験地技術職員の指導のもと、チェーンソーを用いた丸太の輪切り体験を行いました。
上賀茂試験地での実習の後、芦生研究林へ移動しました。夕食後に二つの講義がありました。最初は松岡先生が「芦生研究林の概要説明」という講義を行いました。この講義では芦生の森林や生物多様性とその重要性、そしてシカの過採食による森の変化について解説を行いました。続いて、遠隔地会議システムを用いて、北海道研究林の小林先生が「北海道の森林と人との関わり」についての講義を行いました。
講義後に受講生から、それぞれの身近な森についてパワーポイントを使って説明してもらいました。受講生は、異なる地域や視点を持っていることから、一人ひとり全く異なる「森」の姿や人との関わりの紹介が行われ、とても良い交流の契機となりました。
2日目は、芦生研究林内での見学と調査体験を行いました。午前中は、林内では原生的な自然の残るエリアを歩きながら、天然林と奥山の人工林の観察をしたほか、大規模シカ排除柵の見学を行いました。午後からは芦生のシンボルである大かつらの見学や、トチノキの種子の結実量調査体験とトチノミを利用する文化を守るための芦生研究林と地域協働の取り組みを学びました。
夕方から美山町で暮らす猟師さんから、猟師としての暮らし、「狩猟」と「駆除」の間で生きる葛藤などについて講演をしていただきました。普段は交流する機会のない猟師のお話はとても興味深い内容で、講義後は多くの質問が寄せられました。
夕食は芦生研究林のある美山町で獲れたシカ肉でカレーを作りました。夕食後に張先生が「農山村の生業」という講義を行いました。
3日目は研究林事務所を発つ前に、坂野上先生が「森と人の歴史」という講義を行いました。午前に茅葺の里での里山景観を観察しながら、その歴史や生物多様性との関わりを学びました。
午後には大学構内にある北白川試験地において北山台杉やj.Pod(リブフレームによる木造建築)の見学を行いました。最後に、実習の振り返りが行われ、解散となりました。
学生からは「森林について、人間の利用という観点から歴史や文化について学ぶことができた。森林と人の生活や文化が密接に関わっていることがわかって、森林について学ぶ意義の新たな視点が得られた」、「やはり、座学で習うよりも実際に自分の目で見て、音を聞いて、触ることで得られる知識は、座学で習うよりもスッと知識として頭に入ってくるんだなと実感しました。」といった感想が寄せられました。
3日間という短い時間でしたが、里山から奥山までを観察することができたと思います。この実習を通して森林がもつ魅力を伝えられるとともに、現状の問題点を考えられる人材になられることを期待します。