8月10日を中心に雨風ともに強まったため、天気が回復した11日の午後に研究林内の林道・作業道を巡視しました。
林道・作業道上にはたくさんの落枝があり、倒木も10箇所程で発生していました。
倒木には枝や幹に複雑な力がかかっているため、倒木の処理は特に注意を要する作業の一つです。また今回は倒木の幹にスズメバチが営巣していたものもあり、力のかかり具合だけではなく危険生物が潜んでいないか等、状況の確認にも細心の注意を払って作業をしています。
今回に限らず天気が荒れた後には必ず研究林内の巡視を行っています。
教育・研究活動を円滑に行うためにも、林道等の迅速な点検と対応は必要不可欠な業務です。


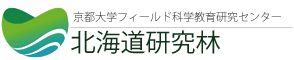























 【標茶】請負で進められていた間伐が終了し、今日はカラマツ丸太の検収をしました。
【標茶】請負で進められていた間伐が終了し、今日はカラマツ丸太の検収をしました。