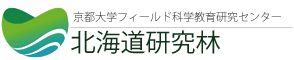北海道研究林では市民の皆様を対象に、標茶区で初夏の花観察会を開催します。
5年に1回(前回は2022年度)、北海道全域で野の花を一斉調査する北海道フラワーソンに準じた内容で行うもので、林内に咲いている花を探してリストアップし、種構成や開花時期の変化を参加者の皆様と一緒に調べます。
植物に詳しくなくても参加可能です。研究林スタッフと観察のポイントを確認しつつ、図鑑片手に花探しに挑戦しましょう。

- 開催日時
- 2024年6月16日(日)10:00-15:30(受付開始9:30)
- 小雨決行
- 開催地
- 京都大学フィールド科学教育研究センター北海道研究林標茶区
- 受付会場は管理棟前(標茶町多和553)
- 駐車場あり、標茶駅への送迎あり
- 定員
- 12名(応募多数の場合は抽選)
- 参加費
- 無料
- 持ち物
- 山歩きのできる(汚れてもいい)服装、歩きやすい靴(長靴推奨)、雨具、筆記用具、昼食、(適宜)虫よけ、図鑑等
- 申込方法
- 参加希望者全員の氏名、生年月日、住所、電話番号、送迎希望の有無を明記し、はがき、もしくはメールにてお申し込みください。メールの件名は「観察会申し込み」としてください。小学生以下のご参加は保護者同伴でお申し込みください。
- 申込締切
- 5月31日必着。抽選結果は6月7日までに郵送、もしくはメールにてお知らせします。
- 申込先
- (郵送)〒088-2339 北海道川上郡標茶町多和553 京都大学フィールド科学教育研究センター北海道研究林
- (メール)hokuken(@マーク)mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
- 問い合わせ先
- (電話)015-485-2637
- (メール)hokuken(@マーク)mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
当日はイベント保険に加入しますが、保険の範囲を超える補償はできない場合があります。個人情報は当イベント運営のみに使用します。
秋には白糠区でも自然観察会を開催予定です。