渓流水のサンプリングの際に変わった形の氷柱を見かけました。
水面ぎりぎりにできた釣鐘状の氷柱です。
雪が解けてできた氷柱が下に伸びることができない代わりに、波によって下から水が供給され続けてこのような形になったと思われます。
上から水が供給される通常の氷柱は上の方が太くなるのと逆といったところでしょうか。
寒さが厳しかった時期には雪も解けず氷柱もできません。
沢もほぼ結氷していましたが、暖気を伴った爆弾低気圧で雨も降り雪も氷も一気に解けてきました。
水のせせらぎに混ざって春を告げる鐘の音が聞こえてくるようです。

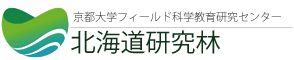


 ついに標茶も雪景色となりました。
ついに標茶も雪景色となりました。








 チョウセンゴミシの実がなっていました。
チョウセンゴミシの実がなっていました。


