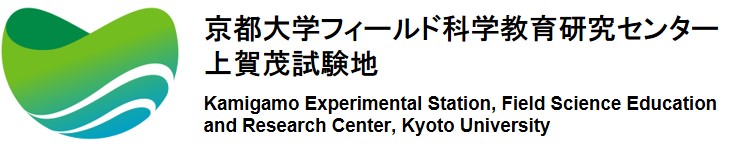3月7~9日に2024年度第11回目の里山おーぷんらぼ(以下、らぼという)が開催されました。今回は本学の学生を主体とする団体「森里海と文化研究会」が中心となってドラム缶を用いた竹炭の生産と竹細工について計画し,実施しました。本学の教員や他大学の学生、高等学校の教諭も参加され、3日間の参加延べ人数は29名となりました。7日は事前準備として、一基目のドラム缶内には、竹割器等で細割し節を除去したモウソウチクを、もう一基には、モウソウチクと広葉樹の枝幹を交互に敷き詰め、投入口を密閉しました。その後、焚口から火入れを行い、缶内部の温度を上昇させ、内部乾燥および木ガスやタールなどの不純物を除去します。一基目は、この日に炭化まで進んだため、焚口を密閉しこの日は終了となりました。翌8日はイベントのメインとなり、参加者の自己紹介の後、田中教員によるガイダンスが行われ、製炭の続きが開始されました。らぼに初めて参加された方には、舘野教員による試験地の案内が行われ、製炭の空き時間にはモウソウチクを用いた細工を行い、ペン立てや巨大な水鉄砲など、多様な作品が出来上がりました。もう一基のドラム缶も炭化まで進みましたが、内部温度が下がらず、この日の炭のお披露目は叶いませんでした。翌最終日には、ドラム缶を開放し、炭の取り出しと出来具合の確認を行いました。安全管理及び記録、サポートのため紺野技術職員と長谷川技術職員が同行しました。







text/長谷川 敦史