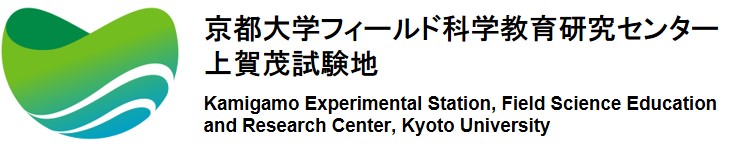2025年6月14日(土)に「ILASセミナー 木文化再生-森林から都市へ」が行われました。当日は様々な学部に所属する本学1回生の学生8名が参加しました。この授業は、森林や里山環境の在り方、日本の木材生産と森林の実態、地域に根ざした伝統木造建築(風土建築)の維持継承、都市木造建築の可能性、木造建築と災害などを概観し、日本の木文化再生について考えることを目的とし、この上賀茂試験地での野外実習を通して、講義で学んだ知識と現場との関連を理解することを目標に開講されています。10時に試験地に集合した後、観察会コースを散策し、京都市の二次林でみられる樹木や試験地に導入された様々な外国産樹木の観察を通して、木材としての利用や用途について学びました。午後は標本館でマツ属やタケ亜科を中心とした標本や、試験地で行っている里山整備の様子を見学しました。その後、上賀茂試験地の歴史と概要について坂野上教員の講義が行われ、最後に質疑応答の時間がとられました。この日は終日雨天でしたが、無事に終了しました。
当日は、記録および安全管理、実習補助として長谷川技術職員が同行しました。







text/長谷川 敦史