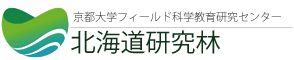10月5日に白糠区で京大ウィークス2024自然観察会「秋の森の生態系」を開催しました。
定員14名のところ応募が31名あり、当日は13名の参加者が集まりました。
観察会は午前中に河畔林コースを歩き自然観察をメインに、午後は林道コースを歩き研究紹介をメインに行いました。
参加者からは「カツラを始め素晴らしい樹木をたくさん見れた。皆さんの活動を知ることが出来た。」「先生がとても丁寧に説明して下さり興味深く学びを深めることができました。」等の感想が寄せられました。
前日まで雨天であったので少し心配しましたが、当日は晴天に恵まれ気持ち良い一日になりました。
来年も標茶・白糠での観察会を予定していますので、ぜひご参加ください。
京大紹介ページ「ザッツ・京大」でも紹介されました。(外部リンク)



(京都大学広報課 提供)