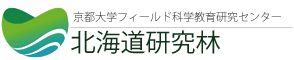6月24日から27日にかけて令和7年度北海道東北地区大学演習林等技術職員研修が京都大学主管で北海道研究林標茶区にて開催されました。
京大での開催は昨年度に続き2年連続で、北海道大学から3名、東京大学から1名、九州大学から1名、京都大学から2名の計7名が参加。本年度は都市部での救急システムでは対応しきれない野外活動を想定し、リスクマネジメントと事故発生時の対処方法について、講義や実習を通して基本的な考え方と技術を身につけることを目的としました。
研修は北海道研究林の職員も加わって、野外や災害時における救急法の講習等を行っているWMA Japanのインストラクターによるセミナーをオンラインにてグループワークを交えて実施したほか、標茶消防署の協力による救命講習会や、各施設で行っている安全対策や事故事例などについての情報共有、標茶区の林内の見学、釧路湿原の温根内木道と野生生物保護センターの見学を行いました。質疑や意見交換を通して、知見を広げる機会となりました。