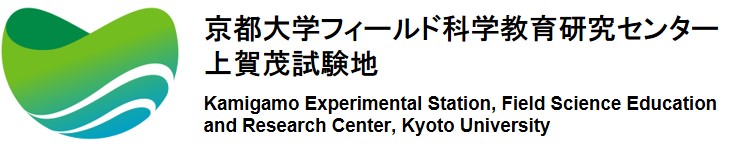2024年11月30日に公開森林実習Ⅲの4回目が行われました。3名の学生のほか、京都大学学術情報メディアセンターの教員1名と学生2名も研究利用のため同行しました。舘野隆之輔教員による講義の後、里山ラボの花壇を少し見学し、実習で植栽する計画についての議論が行われました。午後からは実習地に移動し、藤井弘明技術職員と岸本泰典技術職員によるチェーンソーの解説の後、実際にマツ枯れ被害木の伐倒を見学しました。その後は各自チェーンソー防護衣を装着し、土留め用に準備した細いヒノキの玉切りや伐倒した松の枝払いなどでチェーンソーを体験し、広場に平坦な休憩場所を作る作業に取り掛かりました。学生たちが積極的にチェーンソーの作業を行ってくれたことで、丸太のイスだけでなく幹を縦挽きしたテーブルも完成し、一息つくのにぴったりな休憩場所が出来上がりました。イスやテーブルは、しばらくは松ヤニでべたつくと思いますが、快適に使えるようになるのが楽しみです。
当日は、実習補助及び安全管理、記録のため藤井弘明技術職員と岸本泰典技術職員が同行しました。




text:岸本泰典