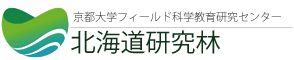8月6日から10日までの5日間、北海道研究林標茶区を主会場に全国の大学生を対象とした公開森林実習Ⅱと、京都大学の1回生を対象としたILASセミナーが同時開催で実施されました。
実習には両実習合わせて18人が参加。天然林と人工林(間伐前後)といった植生による昆虫相の違いをライトトラップやピットフォールトラップを用いて調べたり、道東の自然環境として釧路湿原や川湯のアカエゾマツ林などを見学しました。
霧で見えない時も多いですが、今回は摩周湖がくっきり見えました。日ごろの行いの成果でしょうか。
昆虫採集に夢中な学生も多く、積極的に取り組む姿勢が見られました。