【標茶・白糠】2018.8.23~30にかけて「研究林実習Ⅲ 夏の北海道」が行われ、京都大学農学部の学生14名が参加しました。
カラマツの植栽と間伐、天然林毎木調査、昆虫群集調査、道東地域の土壌断面調査、西別岳登山を予定していましたが、台風19号と20号の影響を受け、昆虫調査は採集地点を減らし、白糠区天然林の毎木調査はスタッフによるデモンストレーションと白糠区構内見本林での樹木解説、西別岳登山は摩周湖外輪及び川湯~硫黄山までの散策にメニューを変更して実施することになりました。
カラマツの植栽と間伐では、現場での作業を実際に体験することで、座学だけでは分からない林業の知見や作業中の安全管理について知ってもらえたと思います。
土壌断面調査は、標茶の研究林内及びその周辺の様々な地点の土壌断面を観察することで、過去の道東地域の火山灰の動向を読み取ることが出来、学生たちは根気強く土壌断面とにらめっこをしていました。
天候に左右されるフィールドワークが主となる実習では、学生の安全を第一に考えることは当然として、せっかくこんな遠くまで来たのだから良い実習、そして良い思い出として残ってほしいという気持ちも重なり、判断はいつも悩ましいです。
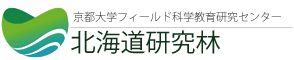










 【白糠】ようやく森の木々が芽吹き始めました。
【白糠】ようやく森の木々が芽吹き始めました。








































