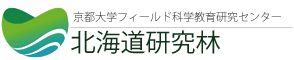6月15日に白糠区にて初夏の花観察会を開催しました。
釧路・白糠周辺から、10代から70代まで幅広い年齢層で、11名の参加がありました。
当日はあいにくの小雨となり、しぼんでいる花も多く、あまり多くの種類は観察できず、早めに観察終了となりました。開花が確認できたのは28種でした。
事務所に戻ってからそれぞれ自分で選んだ花の標本を作製しました。
参加者からは「ハルカラマツとエゾカラマツの違いを知ることができた。」「小さい花を見つけることが難しかった。」「小雨の天気が残念でした。」「知らない花や草などがたくさんありとても面白かったです。」などの感想をいただきました。
雨であまり良い写真が撮影できなかったので、6月10日に下見を行った際の花の写真をいくつか掲載します。
来年は標茶で初夏の花観察会を実施予定です。今度は好天を期待したいです。