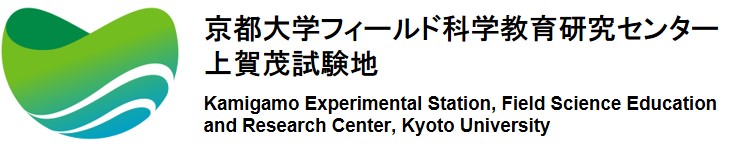5月7日(土)に京都精華大学人間環境デザインプログラム1回生を対象に自然環境演習が実施されました。この実習は、自然環境を観察することで、「自然環境を観察して正しく認識することができる」、「人・モノ・自然環境のつながりを理解することができる」、「人間が自然環境の一部であることを認識することができる」の3つの力を養うことを目的としています。当日は19人の学生が参加し、9時30分よりオリエンテーションを開始しました。10時より德地教授による標本館やガラス室の育苗等の施設紹介が行われた後、炭窯を見学して、製炭に必要な炭材(炭の材料となる木材)の調達と里山更新の関係について学びました。その後、赤石特定助教の解説のもと、京都市でみられる自生種を中心に樹木識別方法を学び、最後に里山に関する実習現場と果樹植栽の現況を見学しました。当日は、西岡技術職員が同行し、実習記録や安全確保を行うと共に、解説補助および技術指導、技術補助に当たりました。






text/長谷川敦史