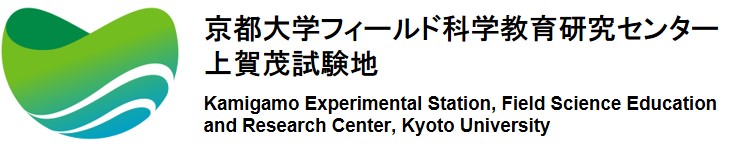例年、芦生研究林で行われていますが、新型コロナによる制限により、今年度は9月28、29日に上賀茂試験地にて振替で行われました。森林の持続的管理と利用のために必要な方法論および基礎的技術について、毎木調査およびチェーンソ-による玉切り体験を通して学習しました。毎木調査では、調査区(プロット)を設定し、プロット内の樹木について、胸高直径、樹高、樹木位置、樹冠幅を測定しました。測定データをもとに、樹木位置図を作成し、樹種構成や林況把握を試みました。玉切り体験では、チェーンソーの取扱いや安全衛生について学び、油圧ショベルの操作も体験しました。