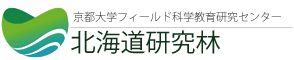【標茶】2016.06.21に沼幌小学校の木工教室が行われました。今年度は天然木を使ったネイチャークラフトで、1~3年生はコースターとペン立て、4~6年生は竹箸と笛に挑戦しました。みんな作業に熱中し、時間はあっという間に過ぎてしまったので、満足できた子もまだまだ物足りない子もいたようでしたが、ケガ無く楽しんでくれたようでホッとしています。
【標茶】野生動物モニタリングとして自動撮影カメラの設置作業中に、エゾハルゼミを見つけました。
羽化したての体は、雨で一層瑞々しさを増し、感動的な美しさでした。
近くには、これから羽化するであろう幼虫の姿も。
標茶区では5/29に初鳴きを観測したので、森はこれからどんどん彼らの声で賑やかになっていくでしょう。


5月27日に標茶小学校の3年生が遠足で研究林にやってきました。3㎞の道のりを歩いてきたのに、元気いっぱいに芝生を駆け回っていました。野生動物や草花の質問も相次ぎ、自然に興味津々な様子を見て、こちらもうれしくなりました。
今年もオオジシギがやってきた

【標茶】ズビャークズビャークという特徴的な声で目が覚めました。北海道には夏鳥としてやってくるオオジシギの声です。
あまりにも近くで聞こえたので、宿舎の窓から目を凝らして探してみると、地面の色に溶け込んだ2羽を見つけることができました。
画像サイズが小さいので、ここをクリックすると大きなサイズでご覧いただけます。
普通救命講習を受講しました
【標茶】4月13日に職員一同が標茶消防署で普通救命講習を受けました。これからも事故のない安全な業務を心掛けていきたいと思います。


【標茶】3/8・9に京都大学技術職員研修が行われました。この研修は、私たち技術職員が他分野の見識を広めることを目的としています。今回は北海道研究林で行われ、農学研究科附属牧場、野生動物研究センター、防災研究所、フィールド研の他施設から計12名が来てくれました。この研修では釧路地方の自然や歴史を学んだり、研究林の見学などを行いました。天気にも恵まれ、楽しく、有意義な研修になったと思います。




【標茶】2/22~2/28の7日間、農学部、薬学部、理学部、工学部、総合人間学部の学生25名を迎えて、「研究林実習Ⅳ・北海道東部の厳冬期の自然環境」を実施しました。
氷点下20度を下回る厳しい冷え込みと澄んだ青空という、まさに冬の道東といえる好天に恵まれ、スノーシューや山スキーを装備しての樹木識別や、積雪調査、毎木調査など屋外での作業をしっかりとこなすことが出来ました。
浜中町の丸善木材の製材工場と釧路市のトドマツ精油抽出プラントの見学は、林業や木材利用の現場を知る貴重な場になったことと思います。
そして、(個人的に)最高だったのは藻琴山に登ったときのすばらしい眺望でした。白い雪原と青い空がどこまでも広がり、オホーツク海の流氷や遠く知床方面まで見渡すことが出来た景色は、実習という枠を超えて、心に残る体験となったのではないでしょうか。
酪農学園大学「生態環境総合実習」(2015年度)
【標茶】2月17~19日に北海道内にある酪農学園大学の「生態環境総合実習」が標茶研究林で行われました。参加した19人の学生は研究林内で冬の樹木観察や積雪調査などを行いました。実習中は天気が良く、冬の研究林を体験してもらえたと思います。




しべちゃアドベンチャースクール(2015年度)
【標茶】1月23~24日、しべちゃアドベンチャースクールステージ5「冬の野外活動」が行われ、小学生16人と高校生8人が参加しました。
開催する週にたくさん雪が降ったため、動物の足跡はほとんど新雪に埋もれてしまっていましたが、雪の結晶や面白い形の冬芽など、子ども達はスタッフと一緒に冬の森でたくさんのものを見つけていました。また、単なる雪遊びやソリ滑りも子ども達にとっては特別な物です。寒さに負けず、冬の野外活動を思いきり楽しんだ2日間になったと思います。


年明けから、気温マイナス10度を下回り、時にはマイナス20度近くにもなる朝が続いています。厳しい気候ですが、澄んだ空気と霧氷のきらめきは、ほんの一瞬ですが寒さを忘れるほどにきれいです。