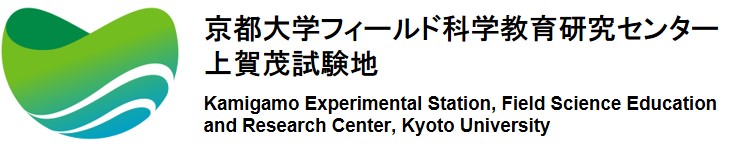この実習は京都府立大学1回生約150名を対象に、4月22日および7月8日、11月18日に行わた。実習の初めに、調査地周辺の天然生林(自然に種子が落ちてできた森林)と人工林(人間が苗木を植えてできた森林)の違いを教員の解説を聞きながら観察し、樹種構成、階層構造ならびに光環境についてそれぞれの特徴を把握した。次に,遷移段階の異なる2つの森林について、植生の階層構造ならびに調査区内の実生(幼樹)の数を調査し、各森林の光環境および温度環境も測定した。最後に得られたデータをもとに、それらの環境要因が森林の様子とどのように関わっているかを考察した。実習には、記録及び安全管理を行うため、西岡技術職員と大橋技術職員が同行した。



text/長谷川敦史