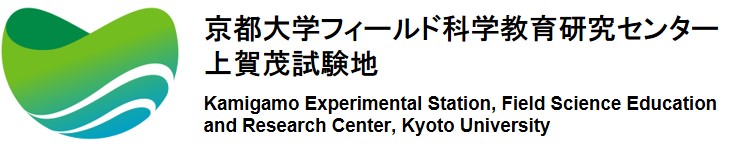10月14日から12月16日までのうち5日間の日程で、他大学学生を対象とした公開森林実習Ⅲが実施されます。この実習は今年度で4年目になり、これから新たな里山を作り上げて、維持管理していくために必要な作業について、実習計画を自ら立案できるノウハウを修得するとともに、計画の実施を自らの責任で行う能力を醸成することを目標にしています。今年度は5名の学生が受講しています。初回(10月14日)は、はじめに教員、受講者同士の自己紹介から始まり、続いて舘野教員によるガイダンス及び試験地概要と里山についての講義が行われました。その後構内を散策しながら温室、資料館、シイタケの圃場を見学しました。午後からは実習地(19林班)まで樹木識別を行いながら道中にある薪割り場や炭窯の見学を行いました。実習地では、学生達が今後どのような事をここで行いたいか協議し、それぞれ色々なアイディアを出し合いました。初回は西岡技術職員が、実習補助及び記録にあたりました。




文:西岡裕平