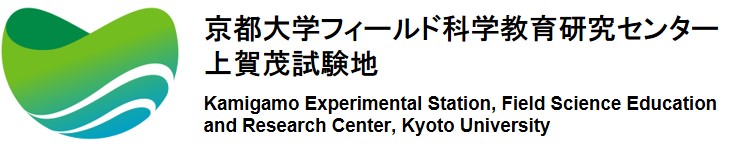3月10日にマツ枯れ防止のための樹幹注入剤を施工しました。樹幹注入は、夏季の薬剤散布と同様に重要な業務で、薬剤散布が不可能な高木のマツや、散布機械が侵入できない場所に生育するマツにも施工可能です。今年度は、例年使用しているマツガードに加えて、新たにマッケンジーという注入剤を導入しました。
マツガードは、マツの幹の太さを基準に施工本数を決め、ドリルで幹を穿孔して薬剤入りのボトルごとその孔に差し込みます。稀に薬害が生じる可能性があるため、施工高さや穿孔角度には十分配慮して実施しています。注入後は、木栓で孔を塞いでいます。



マッケンジーは水溶性の薬剤のため、薬害が出にくく、施工適期が広いことが特徴です。施工方法はマツガードと同様ですが、より小さい孔径にしたり、穿孔深度を浅くできます。施工後は孔を癒合剤で塞ぎました。マッケンジーはゴヨウマツ類への施工も可能であり、試験地で長年懸案であったゴヨウマツ類へのマツ枯れ対策も進めることができます。今後は、これらの薬剤を併用していく予定です。



text/長谷川敦史