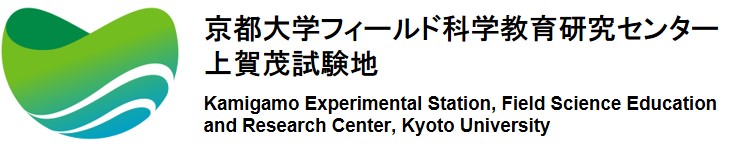苗畑で育成したマンシュウクロマツ(Pinus tabulaeformis Carr.)の新植及び補植と見本樹として植栽していたチョウセンゴヨウ(Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.)の移植を2023年3月に行いました。
新植及び補植
マンシュウクロマツは2007年に導入した種子を翌年に播種し、実生苗を10年以上苗畑で育成して3本が現存していました。育成期間が長く樹高が2m以上となったこと、植栽地と土壌環境が異なること、寄植えに近い状態であったこと等を考慮して、昨年10月に根回し(根元周囲の根系をきれいに切断し、細根を多数生じさせ、移植後の活着率の向上および良好な生育を促す技術の一つ)を行っています。2本は見本園に、残り1本はマツ見本林に補植として植栽しました。根回し期間が不十分だったとはいえ、若い個体のため、細根の発生を期待していましたが、新たな根はほとんど見られませんでした。さらに下部に硬い粘土層があるため、地下方向にも根がほとんど伸長していない状態でした。
 獣害防除(ミキガード)
獣害防除(ミキガード)
新植地では、植穴で生じた土とバーク堆肥を混合して土壌改良を行った後、排水性を考慮して高植えとしました。前日に降雨があり、土壌中に水分が十分に含まれていたため、土極め(植栽種の根鉢に土を細い棒などで押し固め、空隙を少なくして根の乾燥を防ぎ、生育不良を起こさないように配慮すること)を行ってから灌水のみとしました。最後に支柱を設置し、一般的ないぼ結びで樹木を固定しました。試験地では、植栽木への獣害被害が懸念されること、獣害防除対策の省力化を図ることから、苗木の育成期間を長く設定しています。
移植
昨年実施した根回し作業から1年が経過したため、細根の発生を期待しながら掘り進めていきましたが、期待した効果は得られませんでした。根鉢は崩れることなく安定していましたが、念のため根巻きを施しました。本来は根鉢を包み込むようにしますが、今回は簡易的に、幅の狭い麻布を放射状に巻き、その上から荒縄を巻き付けました。
移植場所は近接地のため、重機と小型車で運搬を行い、先の新植と同様に改良後の土で埋め戻しを行いました。
4月に入り、順調に新芽が伸長していることを確認できたので、ひとまず移植は成功しました。今後も生育状況を注視していきたいと思います。
 環状剥皮部からの発根なし
環状剥皮部からの発根なし
 細根も見られない
細根も見られない
 根巻き
根巻き
 埋め戻し
埋め戻し
 二脚鳥居支柱設
二脚鳥居支柱設
record and text / 長谷川敦史