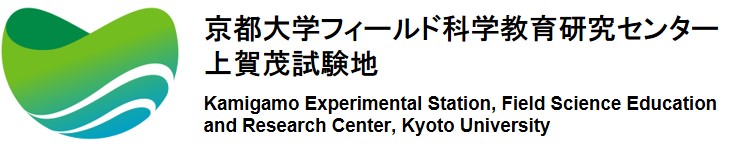5月23日から26日にかけて、モニタリングサイト1000(以下、モニ1000という)に係る各種調査を行いました。モニ1000は「日本の複雑で多様な生態系の劣化をいち早くとらえ、適切に生物多様性の保全へつなげる」ことを目的に、環境省が2003年に始めた事業で、全国に1000か所以上の調査地(サイト)があります。当試験地は2007年より森林・草原調査のコアサイトの一つとして、毎年調査を行っています。今回は落葉落枝・落下種子調査(以下、リター調査という)、セルロースフィルター分解試験、地表徘徊性甲虫調査(以下、甲虫調査という)の3項目について行いました。リター調査は毎月一回、直径約80cmの逆円錐形トラップの中に落下した枝葉や種子を紙袋に回収します。約1haの調査地内にトラップを25個設置しており、月ごとに落下量に差があります。この調査は落葉落枝量や種子生産量の推定や、樹木の更新特性を明らかにする上で重要なデータになります。セルロースフィルター分解試験では、地中および落葉層にセルロースフィルターを埋設し、埋設及び回収時期を変えて、分解の程度を明らかにします。今回は昨年の秋期に埋設したフィルターを、埋設場所近くに付けた目印を頼りに、破らないように慎重に回収しました。甲虫調査は、円柱型のピットフォールトラップを地面に仕掛けて、約3日間、そこに落下する地表徘徊性甲虫を捕獲します。調査地には合計20個のトラップを地面と同じ高さになるように、かつ凹凸を無くすように設置し、落下の妨げとならないよう配慮します。同省が対象とする甲虫類は、温度に対する感受性が高く、寿命が短いため、地球温暖化影響が早期に検出できる生物として重要な位置付けがなされています。
調査に関する詳しい内容はこちら






text/長谷川敦史