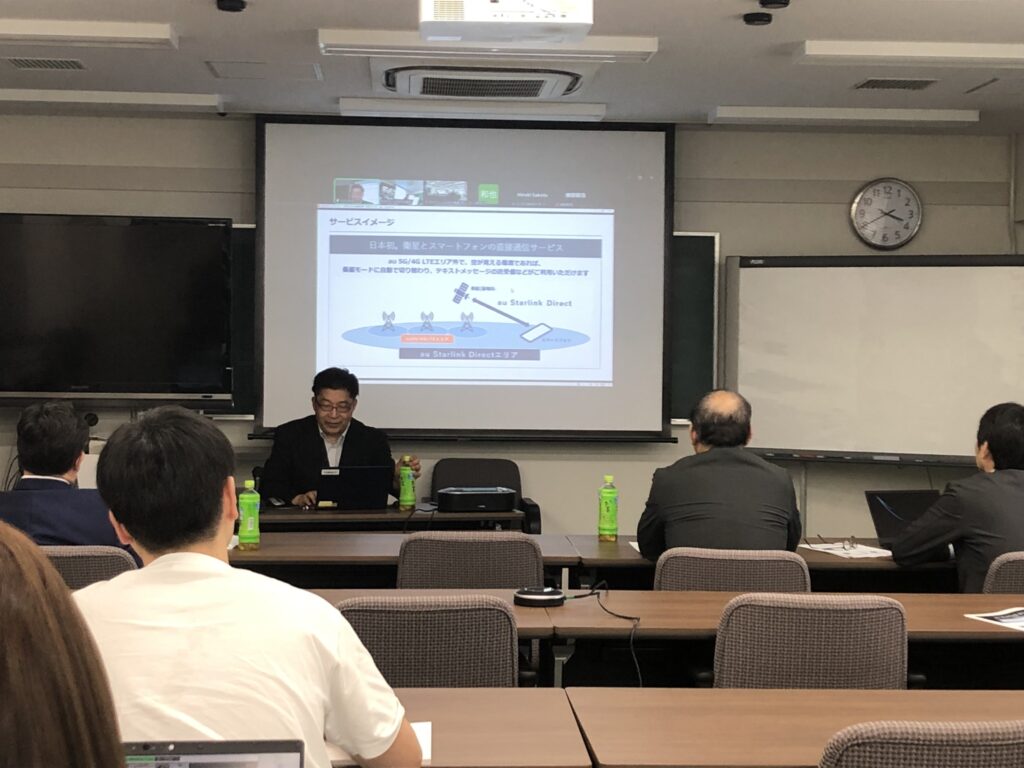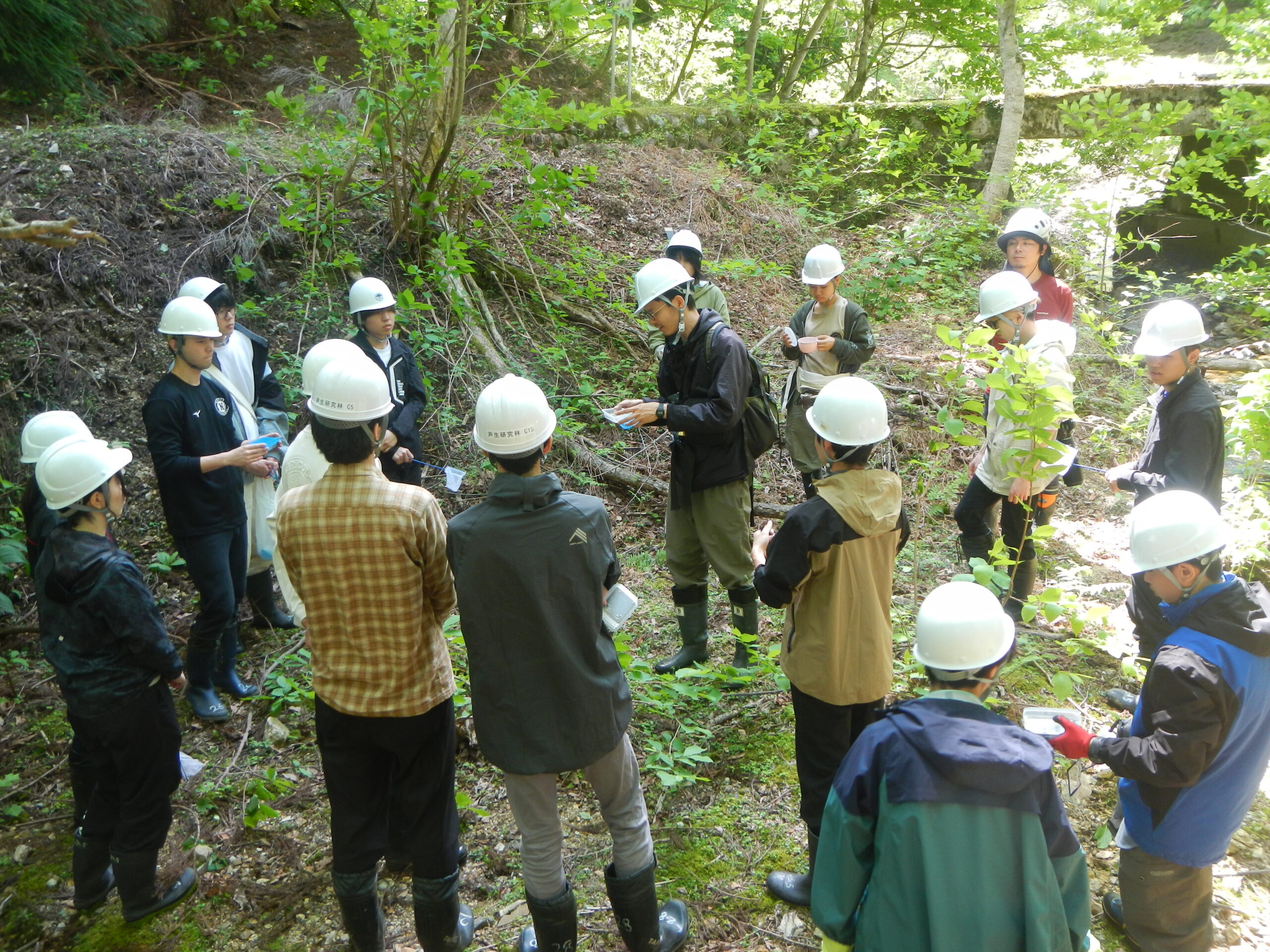ご協力いただき、ありがとうございました。
Thank you for your cooperation.
日頃より研究林の教育・研究活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
今年度は積雪量が多かったため、林道除雪や倒木処理に時間がかかることが見込まれます。
林道整備作業時の安全確保のため、以下の期間は入林を禁止します。
入林禁止期間:2025年4月18日(金)まで
なお、作業の進捗状況によっては期間を延期する可能性がありますので、ご承知おきください。
延期の場合は、判断ができた時点で再度メールをお送りいたします。
また研究林全域にて、銃器を用いた柵内のシカ捕獲を4月30日(予備日5月2日)に行うことが決まりました。
研究林全域入林禁止日:4月30日(水)、5月2日(金)
共同利用者の方等、関係すると思われる方にもご周知願います。
ご不明な点がございましたら、芦生研究林までお問い合わせ下さい。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
Thank you for your understanding and cooperation in the educational and research activities of the Ashiu Forest Research Station.
This year, due to the heavy snowfall, it is expected that it will take time to clear the forest roads and deal with fallen trees.
To ensure safety during the forest road maintenance operations, entry into the forest will be prohibited during the following period:
Forest Entry Prohibition Period: Until Friday, April 18, 2025
Please note that depending on the progress of the work, the entry prohibition period may be extended. If an extension is necessary, we will send another email as soon as the decision is made.
Deer hunting using firearms will be held on April 30 (reserve date: May 2) in the entire forest. You are not allowed to enter the forest regardless of the area.
Forest Entry Prohibition Dates: Wednesday, April 30, and Friday, May 2.
Please inform your co-users and others who may be involved.
If you have any questions, please contact the Ashiu Forest Research Station.
We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding.