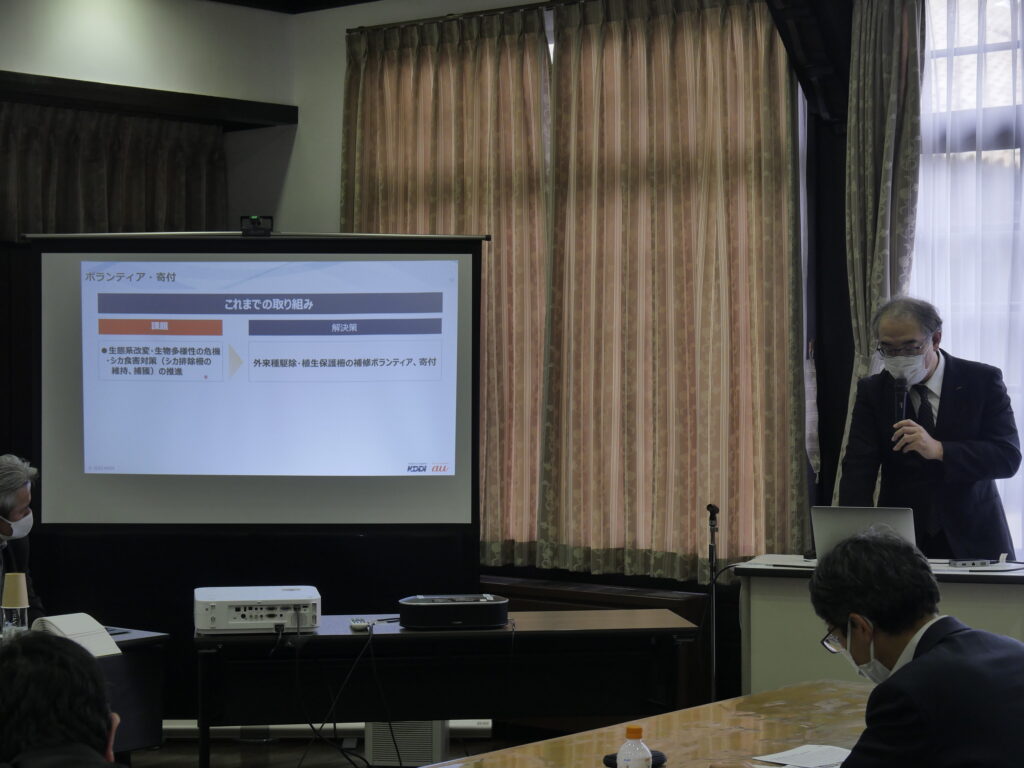8月27日に京都府立植物園において講演会を行います。今年は芦生のキノコに関する話題です。
詳細は下記記載内容をご確認ください。なお事前申込が必要で先着60名様までです。
日時:令和5年8月27日(日)10:00-12:00
場所:京都府立植物園・植物園会館2階 研修室
アクセス:京都府立植物園のウェブサイト(https://www.pref.kyoto.jp/plant/)を参照ください。
参加費:無料 ただし、植物園入園料が必要
主催:京都府立植物園
芦生生物相保全プロジェクト (http://www.forestbiology.kais.kyoto-u.ac.jp/abc/)
京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林
後援:公益財団法人・自然保護助成基金、一般財団法人 タキイ財団
申込(締切8月18日17時):ウェブフォーム(https://forms.gle/61xJHNppHtSRArndA)
もしくは電話0771-77-0321(京都大学芦生研究林)
芦生の森のきのこ世界へようこそ 一年の一時期だけ姿を現す、きのこ。
本講演会では、芦生の森ガイドとともに56年ぶりとなる芦生のきのこ相を取りまとめた赤石大輔氏(大阪産業大学)と、環境DNAを用いた菌類の多様性を研究している芦生研究林の松岡俊将氏(京都大学)から、これまで十分研究されてこなかったきのこの多様性の謎に迫る最新の研究成果についてお話し頂きます。
さらに本年4月に開設されたきょうと生物多様性センターについて平野滋章氏(京都府)にご紹介いただきます。
タイムスケジュール表
司会:阪口翔太(京都大学人間環境学研究科)
| 9:30 | 開場 | ||
| 10:00 | 開催挨拶 | 京都府立植物園園長 | 戸部 博 |
| 10:10 | 芦生研究林でのシカによる生態系改変と 回復に向けた取り組み | 京都大学フィールド科学教育研究センター | 石原 正恵 |
| 10:25 | 芦生のきのこ相を知る: これまでわかったこと(録画放映) | 大阪産業大学 | 赤石 大輔 |
| 11:00 | DNA解析で探る目に見えない 菌類の多様性とその変化 | 京都大学フィールド科学教育研究センター | 松岡 俊将 |
| 11:30 | 京都府における地域と連携した生物多様性保全の取組 | 京都府自然環境保全課 | 平野 滋章 |
| 11:45 | 総合討論 | ||
| 12:00 | 終了 |