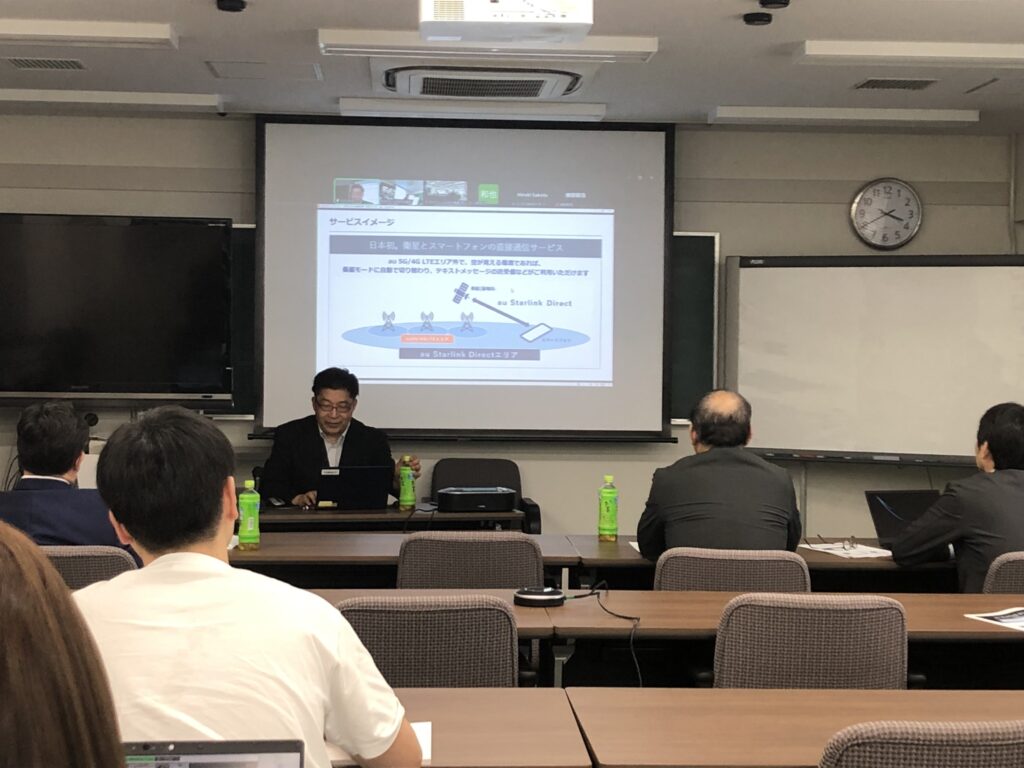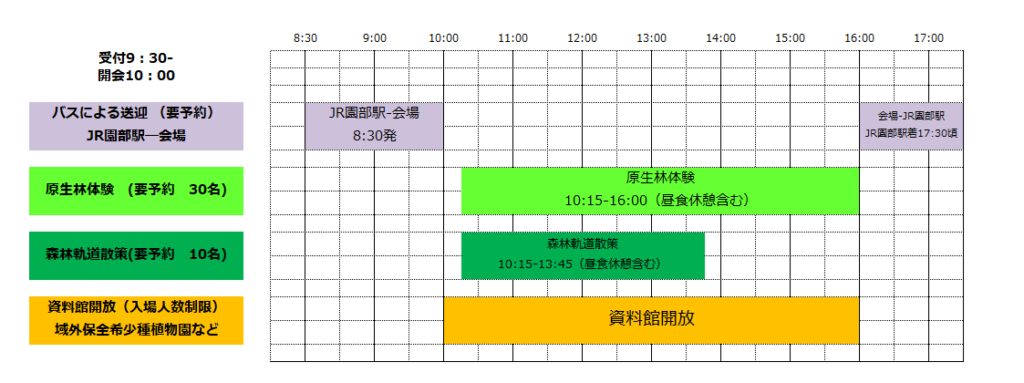7月19-21日に菌類ワークショップ2025を開催しました。本ワークショップは、菌類多様性研究の促進と若手研究者の育成・交流を目的に、教育関係共同利用拠点「人と自然のつながりを学び創る森林フィールド」事業の一環として開催するものです。2023年度の初回から数えて、今回で3回目の開催となります。今年は、若手研究者の講師3名と全国の大学・大学院生10名の参加者が集まりました。
講師として、坂田歩美 (千葉県立中央博物館)、橋本陽 (理研BRC)、升本宙 (信州大学) を迎え、地衣類・微小菌類・きのこといった幅広いグループの菌類について、観察のポイントや最新の研究トピックについてご紹介いただきました。
日中のフィールドワークでは、講師から探索や観察のポイントを教わりつつ、各自が研究対象の菌類を採取しました。フィールドで見られた子実体について、肉眼で確認可能な形質だけではなく、UVランプを用いた蛍光観察や、味の専門的な確認方法など、多角的な同定方法の解説がありました。フィールドから戻った後は、標本の顕微鏡観察と講師の講義、参加者の研究紹介を行いました。参加者の研究紹介では、菌類を軸とした多岐にわたる内容の発表に対して講師や他の参加者から多様な視点のコメントが挙げられ活発な議論が交わされました。参加者にとって、研究の展開や新たな研究の方向性を考えるきっかけになったのではないかと思います。また、講師からは採集された珍しい菌類や未記載と思われる菌類などが紹介されました。
今回のワークショップでは、これまで2回と比べ幅広い研究分野の参加者が集まりました。これから菌類を扱いたい、という参加者も見られ、参加者間での情報交換が活発に行われておりました。また、初めての夏の開催となった今回は、過去のワークショップでは見られなかった冬虫夏草などの菌類も確認され、芦生研究林の菌類多様性を改めて実感する機会になりました。今回採取された標本にも、未記載と考えられる種や芦生新産種が含まれます。今後の解析によって、芦生研究林の菌類相の解明が進むことが期待されます。
フィールド研の研究林・試験地を利用したワークショップは、対象生物やテーマを検討しながら今後も継続的に開催する予定です。2026年度の菌類ワークショップの開催に関しては、フィールド研や芦生研究林のホームページやSNSで情報発信します。