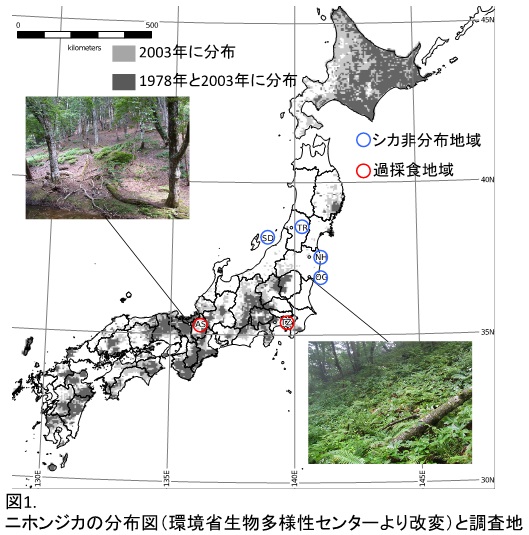概要
芦生研究林は、LIFEPLANという生物多様性調査の国際プロジェクトに参加しています。
右の画像はLIFEPLANのロゴマークです。芦生研究林HP下部のバナーにもあります。

LIFEPLANプロジェクトは、世界の生物多様性の把握を目的として、ヘルシンキ大学が中心となり2021年にスタートしました。
野外では生物の姿を見つけることが困難で、かつ種の名前を判別(同定)するのに専門的な知識が必要です。そのため、どこにどのような生物がいるのかという生物多様性に関する基礎的な情報すら、実はとても少ないのが現状です。例えば、動物や菌類では未知の種が世界中に数百万種いると推定されています(図1)。
LIFEPLANプロジェクトは、世界中の特に動物と菌類を主な対象として、2021年から2025年までの5年間で一斉にサンプリング(試料を採取すること)を行う計画です。現在、世界の140地点ほどで共通の手法による調査が行われています(図2)。

図1. 生物多様性の現状
LIFEPLANのホームページhttps://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan/aboutを参考に作成

図2. 世界各地の調査サイト
※図2中の色は以下の通りです
緑=契約と機材があり、すでにデータを収集している
黄=機材や契約がすべて揃っており、契約や現地の許可が下り次第、サンプリングが開始できる状態
赤=機材や契約が一部不足している
LIFEPLANのニュースレター2023年3月号(https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2023-03/LIFEPLAN%20Newsletter%20March%202023_corrected.pdf)より引用
調査方法・場所
LIFEPLANでは森林にカメラやサウンドレコーダーを設置して生物の映像や鳴き声を捉えたり、昆虫をトラップで集めたり、さらに空気中や土壌中の微生物(きのこやかびなどの菌類の細胞)を収集するなど、我々が肉眼で見つけるのが難しい生物を多角的に捉えようとしています。
さらに、動物や鳥の同定には世界中から集めた画像や音声データとAI技術を活用し、また昆虫や菌類の同定はDNA分析によって行うことで、生物の専門知識を補っています。多様な生物群における分類学専門家の数が減少し、後継者もなかなか育ちにくいという問題が世界的にみられている中で、AIやDNAによる同定の補助は、一つの解決策として注目されています。さらに、サンプルの情報は専用のiPadアプリで管理され、画像や音声データはクラウドサーバーにアップロードすることにより世界中で即時共有されるなど、まさに新しい時代の生物多様性調査プロジェクトといえます。
芦生研究林では、芦生研究林事務所の裏山(Natural Site)と、芦生研究林から約30分離れた美山町の中心部付近の共有林(Urban Site)の2か所でこのサンプリングを行っています。この2か所を設定することで、人間活動の頻度など、異なる環境下での生物多様性の比較検討を行うことができます。
サンプリング
サンプリング対象とその機材は以下の5種類です。

サイクロンサンプラー
自動車用バッテリーでモーターを駆動させ、空気を吸い込むことで大気中の菌類の胞子を集めています。また風見鶏のように風向きに合わせ上部の羽が回転します。胞子はDNA分析され、種や属といった分類群が同定されます。
サンプリングは毎週行っており、1週間のうち2日ほど機械を動かして空気を集めています。

マレーゼトラップ
飛翔性昆虫を集めるテント型のトラップです。昆虫が障害物に当たると上部へ移動する習性を利用し、テント内に侵入した昆虫はトラップの先に仕掛けられているエタノール入りのボトルに集まります。採取した昆虫はカナダでDNA分析による同定が行われます。

自動撮影カメラ
赤外線センサー付きのカメラで、熱を持ち動くものに反応して撮影を開始します。哺乳類の撮影のために設置していますが、たまに日光に当たった葉にも反応してしまいます。夜間も比較的きれいに撮影できます。撮れた動物の画像からAIによって種を判定することを目指しています。
防水・飛来物対策として、園芸用プランターを半分に切断したものを取り付けています。中で蛾が蛹になっていたことがあります。

サウンドレコーダー
録音時間や時刻、周波数を定め、音声を録音できる装置です。鳥類の鳴き声を録音する目的で設置しています。10分毎に周波数の異なる2タイプの音を録音していて、AIによって音声から鳥類の種を判定する計画です。
毎週専用のアプリを用いて時刻の補正を行っています。

コアサンプラー
調査地の土壌を採取することで、土壌中に含まれる菌類を採集します。100mlの土を採取できるコアサンプラーを用いています。
菌類はDNA分析によって同定されます。
自動撮影カメラに写った動物の紹介






LIFEPLANプロジェクトについてより詳しくご興味をお持ちの方は、ヘルシンキ大学のLIFEPLANサイトをご覧ください。