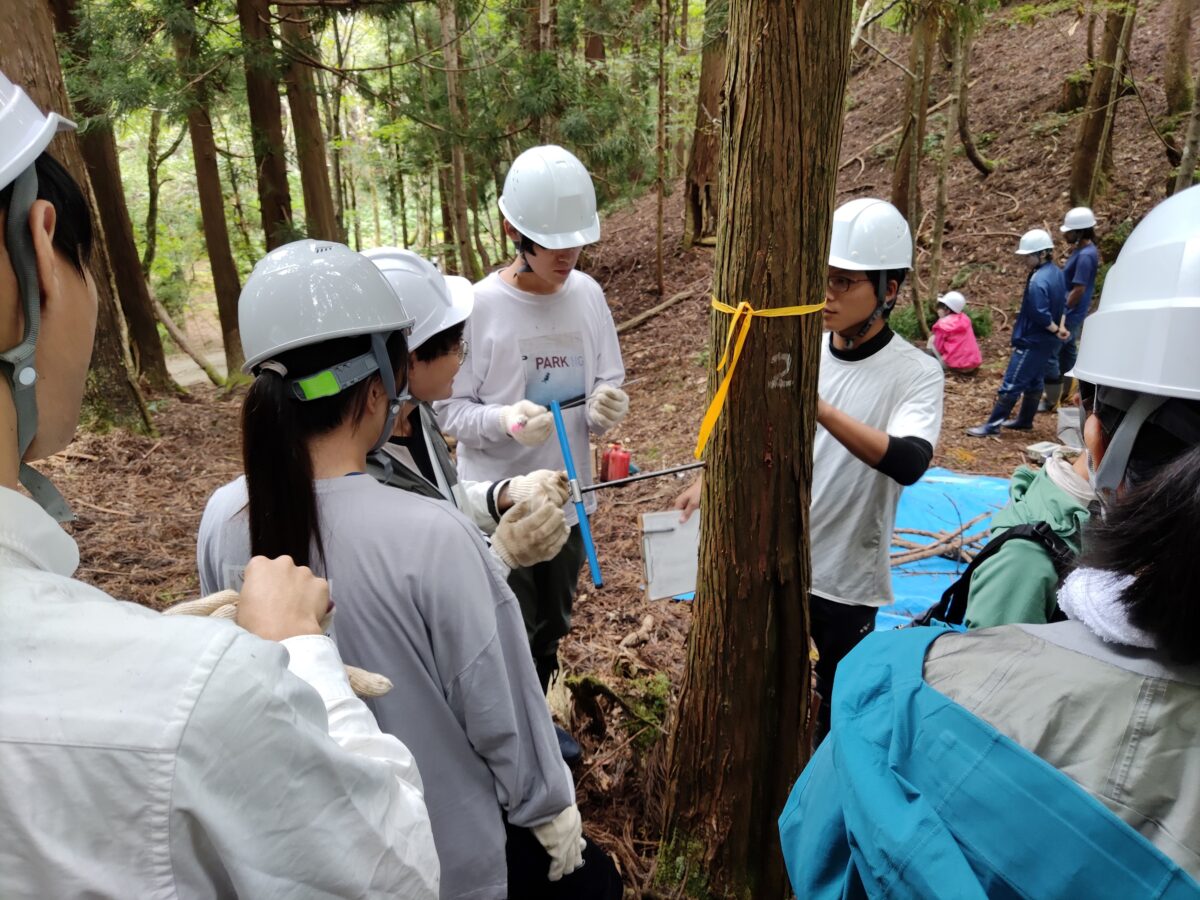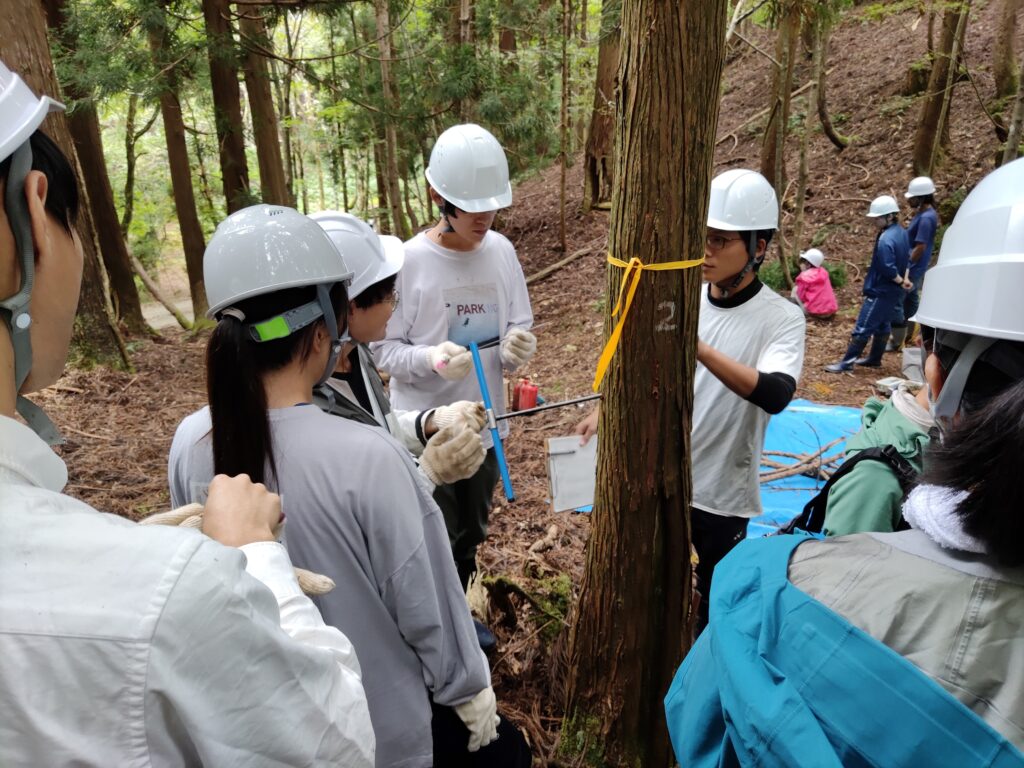2024年8月6日~8月10日
上記日程で2024年度森里海連環学実習Iを開催し、京都大学から5名、他大学から4名の計9名の学生が参加しました。この実習はフィールド研が開催している公開実習の一つで、京都大学に所属する大学生のみならず、他大学の大学生も参加することができます。
この実習では芦生研究林内から若狭湾にそそぐ「由良川」を調査フィールドに設定しています。実習の目的は、水生生物の調査や水質分析を通じ、森から海までの流域を複合したひとつの生態系として捉える視点を育成する事です。
1日目はまず、研究林内にて大カツラの見学や、河川源流域(由良川支流)での生物観察などを行いました。見学等を行った後、事務所付近(由良川上流部)に移動し、魚類・水生昆虫・付着藻類・河川水のサンプリングと水質調査を行いました。その後、由良川の中流域である京丹波町和知B&G海洋センターで同様の調査を行いました。
この日は2地点で調査を行った後、フィールド科学教育研究センターの施設である舞鶴水産実験所に移動しました。
2日目は由良川中流域から若狭湾まで、初日と同様の調査を4地点で行いました(河口と海では魚類、プランクトンおよび水試料のサンプリングと水質調査)。2日間で森から海までの6地点で調査を行いました。
3日目は採取した水試料および付着藻類の分析と水生昆虫と魚類の観察と同定を行いました。
なお,芦生研究林の技術職員2名が実習3日目まで、実習補助と実習中の安全確保を目的として同行していました。また、実習の事前準備として、中流域の調査地点の河川敷の安全確保のための草刈りと下見を技術職員4名で行いました。
4日目は水試料および付着藻類の分析を行った後、得られたデータの整理と発表に向けてのまとめを行い、5日目に実習成果の発表を行いました。
実習成果の発表は3つのテーマ(魚、水生昆虫、一次生産者(付着藻類とプランクトン))を設定し、各テーマと水質を関連付けた解析とまとめを発表してもらいました。解析時間もデータも限られたものの、グループごとに集中して発表準備を進めていました。
今回初めて付着藻類の調査を実施しました。分析には時間や手間がかかったものの、定量的なデータ(河川の付着藻類量と、全地点のクロロフィルa)を得ることができ、河川の一次生産者についての解析と地点間比較が可能になりました。
参加した学生からは「一つの川の上流、中流、下流、支流など様々な地点から観察を行うことでその繋がりを見出し理解できるようにスケジュールが組まれていたこと。そのおかげで、実習の内容がより深く理解できたと思います。」といった実習内容に関する感想の他に「先生やTAの方がしっかり付いてくださって、お話をしやすい空気だったのがよかったと思う。」といった、実習の雰囲気も良かったという感想も複数いただきました。