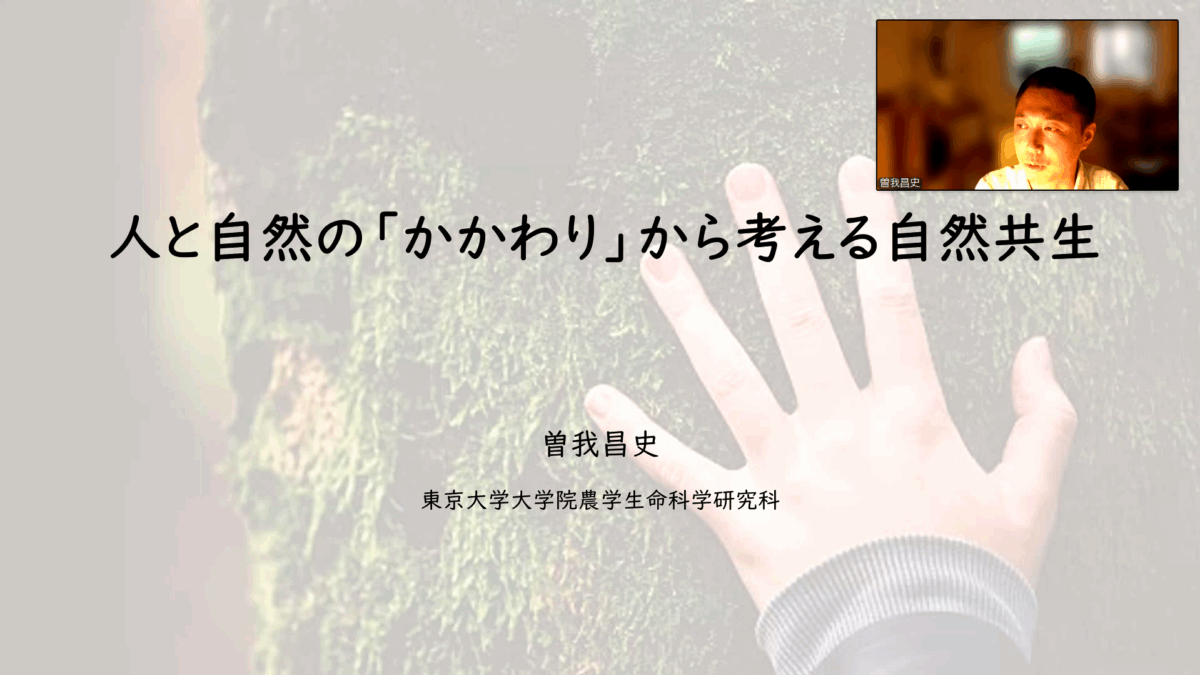森林情報学分野 松岡 俊将
2025年8月19日に、新しい里山里海の勉強会をオンライン開催しました。この勉強会は、京大フィールド研とイオン環境財団が協働している「新しい里山・里海 共創プロジェクト」が主催しており、私たちの暮らしや生物多様性を含め様々な側面から里山里海を学び、これからの里山里海のあり方や活かし方を考える機会として開催しています。勉強会は、全国の里山里海の研究者や実践家を講師に招いての講義と、フィールド研の研究者や参加者同士の意見交換という2部構成で行われます。
第11回となる今回の勉強会では、講師として東京大学大学院農学生命科学研究科の曽我 昌史准教授に「人と自然の「かかわり」から考える自然共生」について講演していただきました。曽我さんは、群集生態学や保全生態学をバックグラウンドに持ちながら、現在はアンケート調査などを含めることで、人と自然のかかわりについて多角的にアプローチ・分析されています。
講演では、人と自然のかかわりの現状と重要性、そして現代における自然体験の場についてお話をしていただきました。まず、現在世界中で人と自然のかかわり(自然体験)が急速に減少していることが紹介されました。その要因として、都市化に伴う自然体験の機会の減少や世界規模での生物多様性の消失を指摘されました。さらに、自然体験の減少に伴って、自然に対するネガティブな感情(生き物が怖いなど)が増加する一方で、自然体験があると自然の価値を認識しやすく生態系の保全行動が高まるという、自然体験がその後の感情や行動に繋がる例が紹介されました。
次に、自然体験の重要性として、健康効果について紹介していただきました。自然体験をすることで、身体・精神の健康が増進し、社会的孤立感を感じにくくなるなど、自然が人の健康に貢献するという豊富な研究例を紹介いただきました。こうした自然体験が人にもたらすポジティブな効果を認識することで、自然への興味と自然体験の増加、そして生物多様性や生態系の保全という好循環に繋がっていくことが説明されました。
最後に、この好循環を生み出すには、自然体験の場として地域の環境保全・環境教育活動が重要であることを解説いただきました。特に都市部や近郊の活動は、安全かつ体験のハードルが比較的低く、さらに人同士の交流も促進する場としても働いているということが説明されました。
参加者からは、「自然体験について自身で直観的に感じていたことを、体系的に言語化して頂き、思考がすっきりした」「自然の重要性について身体的健康など様々なエビデンスがあることを知り、自信をもって仕事を通じて環境教育を広めていきたいと感じました」といった感想をいただきました。また、第2部の意見交換では、第1部で説明された自然体験の重要性を踏まえ、都市部での自然体験(イベントや緑地)をどのように増加させるか、また安全な自然体験の場をいかに用意するか、など活発な議論が行われました。
(参考)新しい里山里海の勉強会(オンライン・第11回) 開催案内
ニュースレター67号 2025年11月