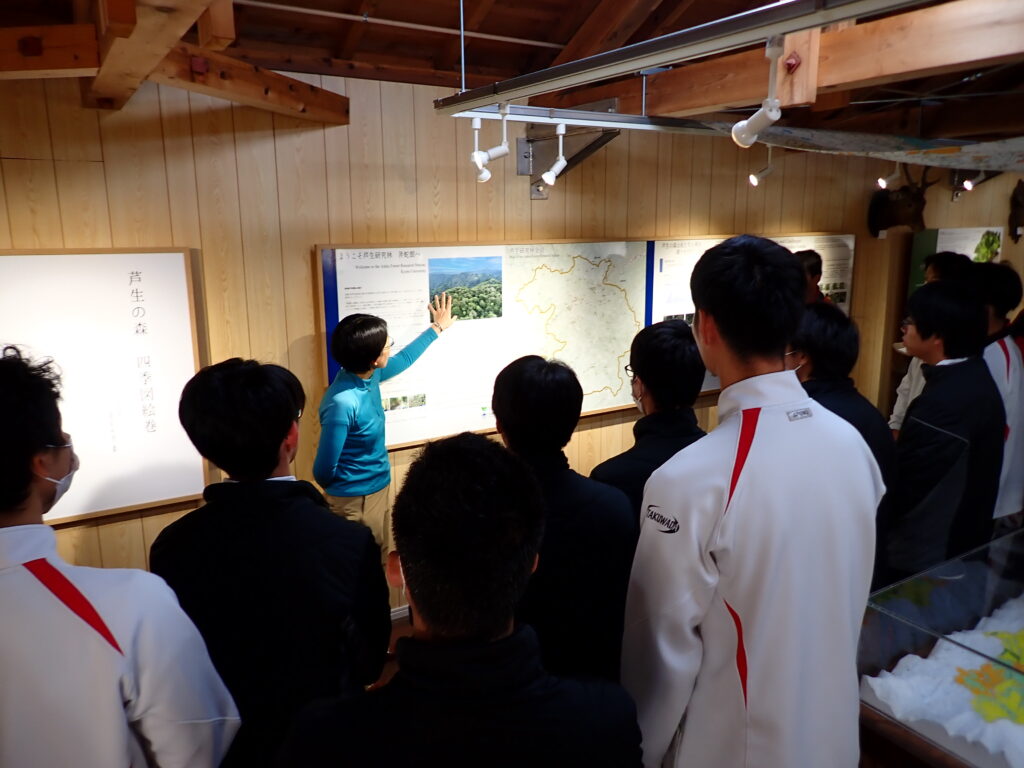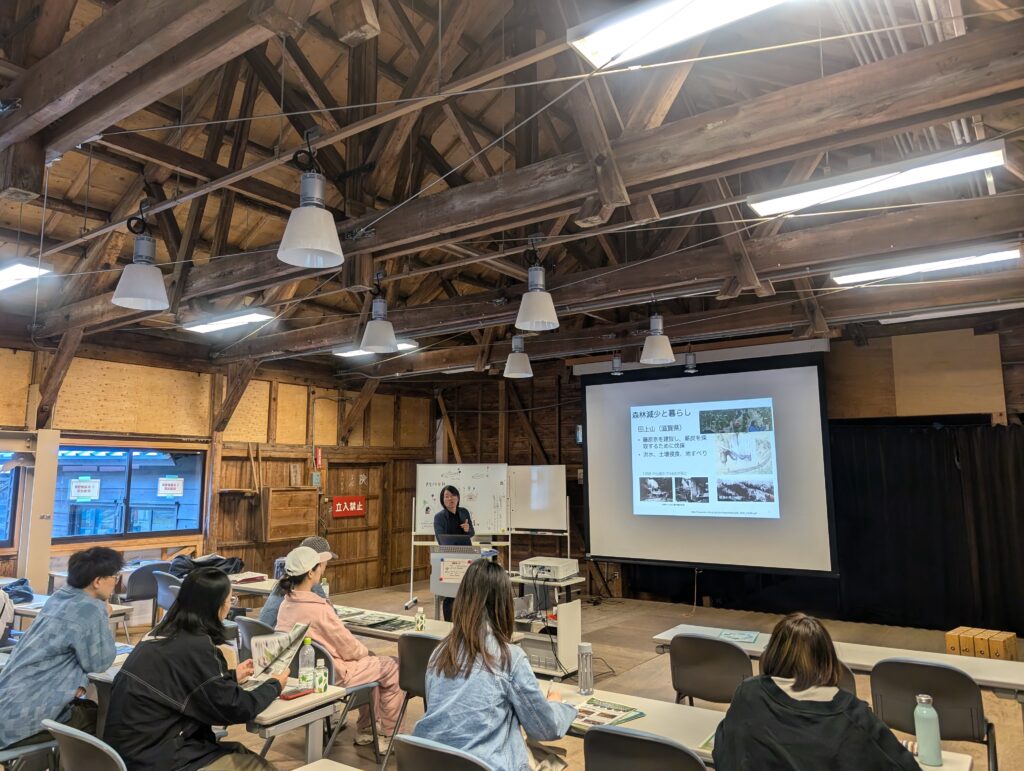2024年9月11日から13日の日程で、京都大学のILASセミナー「京都の文化を支える森林:地域の知恵と生態学的知見」が開催され、文学部・理学部・医学部・農学部・工学部の1、2回生9名(うち1名はコロナのためオンライン参加)参加しました。
京都は豊かな森林・水などの自然に支えられ、その資源を利用することによって古より発展を遂げてきました。多くの文明が環境破壊と生態系サービスの劣化によって失われた事実とは対照的に、京都の周辺は現在でも多くの森林や渓流が残り、京都の文化を支えています。
本科目は、京都文化を支えるこれらの自然の利用方法や森林に対する人々の知恵を知り、森林と人間の関係を科学的に捉える研究手法を実習を通して学び、人間社会と森林との新しい関係を考えることを目的としています。
1日目は、かつての里山、現在は都市近郊林である上賀茂試験地で行いました。里山の典型的な樹種やナラ枯れを観察し、炭焼き窯を見学し「新しい里山」としてのイオン環境財団との連携事業を学び、チェーンソー体験を行いました。その後、芦生研究林へ向かい、夜は芦生研究林の概要について講義を行いました。講義後は学生さん同士で交流を深めていました。
 チェンソーの説明
チェンソーの説明
 炭窯の見学
炭窯の見学
2日目は、原生的な森林である芦生研究林で、天然林とそこに生育する樹木などの生き物や大規模シカ柵内外の植生の見学を行いました。午後からは、栃の実の生産量や利用に関する調査を行いました。下山してから、「農山村・自然から学ぶことの大事さ」と題して、筑波大学大学院生の森山久美さんに講演していただきました。彼女は、小学生のときに山村留学で美山町に来られ、それがきっかけとなり、筑波大学で野外自然教育の研究をされています。とてもわかり易く、自然教育の意義や、美山町などの農山村や自然から私たちが学ぶことを講演してくれました。
森山さんの講演に対し、「今後の進路についての質問に森山さんが『いずれは博士課程に進みたいけれど、今進んでしまったらこの土地のことを何も知らない研究者になってしまう。』と答えていたのが印象的だった。ただ研究者になるという夢ではなく、そのような研究者になりたいのか、そのためには何が必要か考えている姿を見て、自身も医療の道で研究をしたいと考えているため、研究者には現場のことを知っている、現場のことを考えている、現場やそこにいる人々に寄り添っているという要素が必要だと感じた」との学生さんからの感想もありました。
3日目は、美山町の茅葺の里、京北町の木材市場「北桑木材センター」を見学しました。その後、北白川試験地へと移動し、北山台杉、間伐材を有効利用した建物、材鑑標本を見学しました。
今年は例年以上に、多様な学部の学生さんが受講しており、着眼点が多様でした。例えば工学部の学生さんからは、「今回の授業で得た学びの中でも特に印象に残っていることが、里山での木の生え方、そして森林と建築の木材を通じた関わりです。特に後者については建築物のどの部分にどのような木材が使われるのか、そしてどのような過程を辿って伐採された木が建材として利用されるのかを直接自分の目で見れたことは(就くかはわかりませんが)建築士となった時に大いに役立つと思います。このような体験をさせていただきありがとうございました。」という感想が寄せられました。
「今回の実習で人生で初めてスマートフォンもつながらないような奥山に行った。事前講義で学んだシカの増加の影響は普段生活するにあたってほとんど感じたことはなく、問題の重大性と緊急性はほとんどわからなかったが、実際山に入ってみると、地面にはシカの食害によりほとんど植物は生えていなかったし、樹木の樹皮も食べられてしまっている様子を見ることができて、この問題が実際にどんな影響を与えているか分かった。シカ柵の向こう側と全く様子が異なっていた。そしてこれまで同じような緑としか認識していなかった森林にはたくさんの樹種があり、よく見てみると中には枯れてしまっている木もあって普段の視野の狭さ、知識不足を身に染みて感じた。上賀茂や美山の里山との違いも分かった。里山は実際に人間の生活があって、昔のやり方とは異なるけれども守られている伝統がありこれを私たちは継承していく義務があるのだと感じた。森林にはたくさんの資源があって貴重な財産である。これは必ず守っていかなければならないものだ。初めて他人事ではないと感じた。」
また、コロナ禍の影響をうけた学生時代を過ごし、またデジタル・ネイティブな学生さんたちにとって、芦生研究林での宿泊を伴う実習とはどのような意義を持っているのかを担当教員に改めて認識させてくれる感想もありました。
「今回の実習の本来の意義とは少し関係ない感想にはなりますが、カレー作りや自然の家での宿泊など、小学生の頃に体験した喜びを改めて感じることができました。特にネット環境のない場所で友人たちと過ごす時間は、現代に生きる私たちに大切なことを思い出させてくれました。例えば、トランプゲームを通して生まれた高揚感や、自然の中で過ごすことで得られる心の安らぎなど、デジタル機器に頼らない対話の楽しさを再認識できたことは大きな収穫でした。一実習生が言うのもおこがましい限りですが、人々と触れ合う楽しさを思い出させてくれたこの実習を来年以降も是非続けてほしいと思います。」
「芦生研究林での合宿の、2日目の夜に食べたシカ肉のカレーがとてもおいしかったのもとても印象に残っている。シカの食害による山林での生態系の破壊が大きな問題になっているが、シカ肉のおいしさをもっと広めていくことで、シカの食害を食い止める上での一助になるのではないかと思った。」 学生の皆さん、猛暑のなか、お疲れ様でした。今後社会に出ていっても、森と皆さんの生活のつながりを忘れないでいてほしいと思います。
 樹木解説の様子
樹木解説の様子
 シカ柵の説明
シカ柵の説明