男女共用だった学生宿泊所の大浴場を改修し、個人用ユニットバスとシャワーブース(全5室)が完成しました。脱衣所も含めて全てのユニットを完全に個室化しました。
芦生研究林では、誰もが安心して利用できる環境を目指した施設整備を進めています。




男女共用だった学生宿泊所の大浴場を改修し、個人用ユニットバスとシャワーブース(全5室)が完成しました。脱衣所も含めて全てのユニットを完全に個室化しました。
芦生研究林では、誰もが安心して利用できる環境を目指した施設整備を進めています。




2023年3月9日、芦生研究林およびKDDI株式会社は、京都大学 旧演習林事務室ラウンジにて、
生物多様性の保全に向けた包括連携協定を締結しました。
国立大学法人京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林 (所在地: 京都府南丹市、林長: 石原正恵、以下 芦生研究林) とKDDI株式会社 (本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 髙橋 誠、以下 KDDI) は、芦生研究林の生物多様性や生態系の保全・教育・研究の促進に寄与することを目的に、包括連携協定 (以下 本協定) を締結しました。
1990年代の後半から、芦生研究林の貴重な植生が、個体数が増えたニホンジカの採食によって著しく衰退してしまいました。植物だけではなく、昆虫や魚などの様々な生き物や、土壌、河川にも影響がでており、生態系の改変が進み危機的状況となっています。
両者は本協定を通じて、芦生研究林の生態系や生物多様性の保全、芦生研究林に関する教育研究活動・
普及啓発活動、DXや通信技術などを用いた芦生研究林に係る活動の発展高度化に取り組みます。
■ 本協定の内容
1. 協定の名称:芦生研究林の生物多様性等の保全・教育・研究の促進に向けた包括連携協定書
2. 協定締結日:2023年3月9日
3. 協定締結の目的:芦生研究林の生物多様性や生態系の保全・教育・研究の促進のため
4. 連携事項:主に以下分野について、連携し協働します。
・芦生研究林の生態系や生物多様性の保全
・芦生研究林に関する教育研究活動、普及啓発活動
・DXや通信技術などを用いた芦生研究林に係る諸活動の発展高度化
(出席者)
KDDI株式会社関西総支社 田中 稔 社長
KDDIエンジニアリング株式会社 髙畑 謙吾 取締役執行役員
公益社団法人京都モデルフォレスト協会 廣居 恵祐 常務理事兼事務局長
京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林 石原 正恵 林長
報道発表資料
京都大学芦生研究林とKDDI、生物多様性の保全に向け包括連携協定を締結PDFファイル ・ 協定書PDFファイル ・ KDDIウェブページ



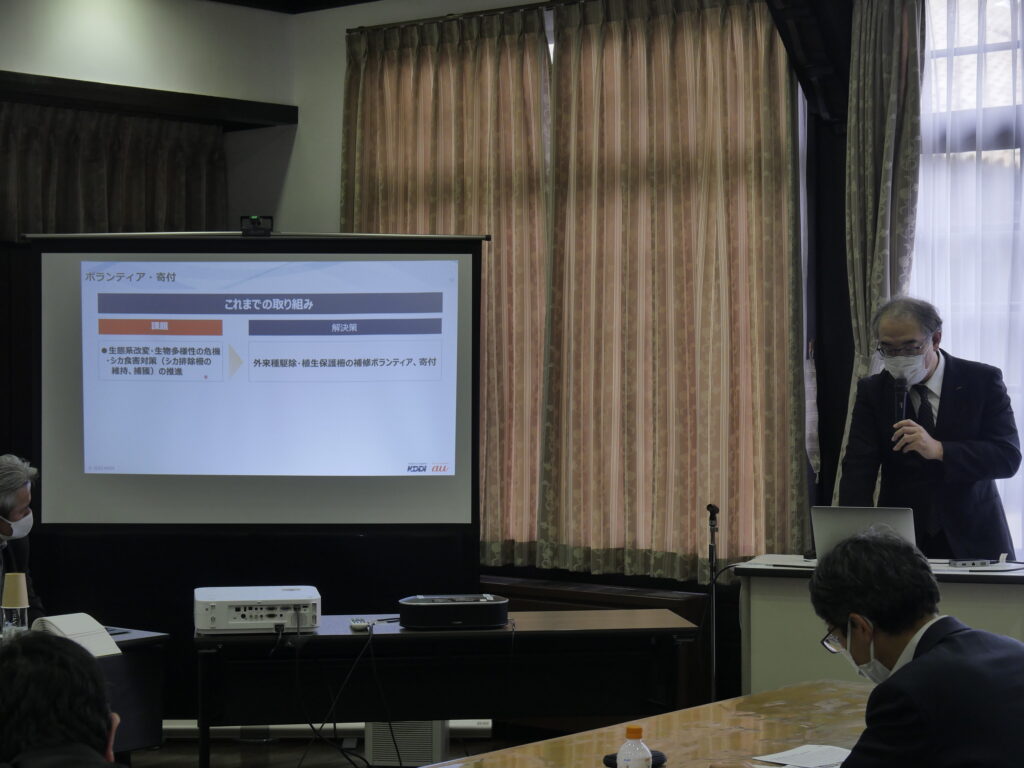




2022年6月18日(土)ロームシアター京都にて京都大学創立125周年記念アカデミックマルシェが開催され、フィールド科学教育研究センター芦生研究林が「森林VR体験」をKDDI株式会社様にご協力いただき出展致しました。
当日は天候にも恵まれ、128名という多くの方に、芦生研究林内の森の四季やシカの食害についてのVR動画の体験をして頂くことが出来ました。体験頂いた方からも「芦生に行ってみたくなった」、「昔、芦生に行った時のことを思いだした」、「シカの食害がこんなに深刻な問題だと初めて知った」などのご意見を頂きました。
森林をバーチャルで体験するという技術を通じ、芦生研究林の魅力や課題についてより多くの方に知って頂けたのではないかと感じています。
森林VR動画はコロナ禍、ポストコロナにおけるフィールド実習を補う教材として、また、より多くの方に芦生研究林へ関心を持っていただく導入として活用しています。
この森林VR動画は、舞鶴工業高等専門学校ハンドメイド部様、KDDI株式会社様にご協力いただき制作いたしました。






芦生研究林と KDDI 株式会社は、芦生研究林の貴重な自然の保全と、バーチャルリアリティ(VR)を活用した最先端な大学教育などについて連携しています。2021年度にKDDIから紹介いただいた舞鶴工業高等専門学校 HANDMADE部と共に、芦生研究林の魅力や危機を伝えるVR動画を3本制作しました。
この3者共同プロジェクトの成果発表と動画作成のお礼として、2022年9月28日に、舞鶴工業高等専門学校への芦生研究林、KDDI株式会社による感謝状贈呈式および、VR連携成果発表会を開催しました。芦生研究林林長、赤石大輔助教、永井技術職員らが舞鶴工業高等専門学校へ伺い、HAND MADE部の部員の皆さんへ、感謝状を贈呈いたしました。KDDI関西総支社の田中稔総支社長や動画制作に関わった社員の皆様にもご参加いただきました。
芦生研究林では、鹿の食害による下層植生の衰退と生態系改変が大きな問題となっており、この状況を広く社会へ知っていただくことで、保全活動へのご支援を募ってきました。また、コロナ禍の中、芦生研究林での学生実習の実施が困難になり、どのように学生の教育を実施していくかが課題となっていました。このような状況下で、新しい技術であるVRを使って、学生をはじめ多くの方に芦生の自然と課題を知ってもらいたいというのがVR動画の制作を決めた理由の一つでもあります。
動画制作の部分を舞鶴高専HANDMADE部へ依頼し、研究林の見学やオンラインでの打ち合わせを重ね、約1年かけて3本の動画を完成させました。完成した動画は、2022年6月18日に開催された京都大学125周年記念マルシェで一般公開し、多くの方にご試聴いただきました。
HANDMADE部の皆さんには、動画の編集からナレーションまで全て行っていただき、素晴らしい動画が完成しました。打ち合わせを何度も行い、研究林側からの度重なる修正の指示を辛抱強く受け入れ、対応してくださった部員の皆さんに大変感謝しています。
感謝状贈呈式で久しぶりに部員の皆さんとお会いして、短い時間でしたが製作時のことを振り返る意見交換をしました。少し時間が経っていましたが、いろいろな話題が出て、話がつきませんでした。部員の皆さんにとって、芦生研究林にご協力いただくなかで学びとなり、また企業・大学との連携の経験やVR動画制作で獲得した技術や知識が今後活かされれば、芦生研究林の教職員一同としてとても嬉しく思います。
京大フィールド研が提唱する「森里海連環学」は森と海の、そして人と自然のつながりを考え、つながりを再生してくために社会と共に実践していく学問です。芦生研究林が由良川の上流から呼びかけ、KDDIという企業がつなぎ、由良川河口の舞鶴の学生が動いたこの取り組みは、まさに森里海連環学の実践事例と言えるでしょう。このような連携を今後さらに発展させていきたいと考えています。



以下、感謝状贈呈式での石原正恵林長の挨拶:
「本日は感謝状贈呈式及びVR連携成果発表会にご参集いただきまして大変ありがとうございます。
私は根っからのフィールド屋ですので、実を申しますと、KDDI様との連携が始まった2020年当初、VRには懐疑的でした。所詮、バーチャルはリアルにはかなわないと思っていました。しかし、静止画のVRコンテンツができあがり、それを新型コロナウィルス感染症により中止した実習の受講学生さんに体験いただいきました。そのとき、学生さんがとても驚いて、そして笑顔で帰っていきました。
こうしたことから、コロナ禍でのリアルな実習ができない場合の代替として利用するだけでなく、リアルな実習での学習効果をより高める教材として活用できることを確信するようになりました。
一方で、いつも率直な意見を述べてくれるガイドさんや、子どもたちからは、森の中を歩けたらいいのに、音がほしいなど手厳しいコメントがありました。そこで動画に取り組みたいと考えていましたが、動画となると一気に編集などの手間が増え、芦生研究林の教職員とKDDI様だけでは制作はできないことが課題でした。そこに、舞鶴工業高等専門学校HANDMADE部様のご協力が得られることになり、3本ものVR動画が本年度のはじめに完成しました。
早速、本年度、多方面で活用させていただいてます。まず教育面では7つの実習において133名の学生が体験しています。そのうち、8月に実施した森里海連環学実習でも活用しました。この実習では、由良川の源流である芦生研究林からスタートし、途中、水質やプランクトン、魚などをサンプリングしながら、由良川をくだっていき、最終的には河口に位置する舞鶴市にある京都大学の京都大学舞鶴水産実験所まで行きます。この過程で、森と海の繋がり、そして人間社会と森や海のつながりを学びます。この実習では、コロナの感染予防のため芦生研究林での実習時間が短縮せざるを得ませんでしたが、VR動画を活用し、シカの食害など森の学びを充実させることができました。
次に、一般の方向けのイベントでは、3件、304名の一般の方にご体験いただいてます。芦生の森を守っていこうという気持ちがより多くの方に伝わるようになり、芦生研究林へのご寄付を呼びかけることができました。この後も、京都大学一般公開「京大ウィークス」や実習などでの活用を予定しております。
さらに、本成果は、全国的なつながりへと発展しています。全国の大学演習林や研究サイトで作られたデジタルコンテンツのカタログとなるように、「デジタル森林教育コンテンツ」ウェブサイトを京都大学と北海道大学が中心となり作成しました。こうしたウェブサイトをつうじ、本VR動画が、芦生研究林だけでなく、広く森林教育に関わる人にご利用いただける可能性が広がってきています。
コロナ禍を機に日本社会、そして世界は大きく変わりました。学生の皆さんには、学びの機会が制限され、友達との体験も制限され、とてもつらかったろうと思います。しかし、コロナ禍がきっかけとなり、このようなご縁に恵まれ、バーチャルとリアルをつなぎ、空間を超えた対話と連携が生み出されました。
この経験が、これからの社会を切り開いていかれる学生の皆様にとって、少しでも力となり、自信となれば、教育機関としての京都大学芦生研究林として嬉しく思います。また我々も、舞鶴高専の学生さんの良いものを作り上げたいという若い真摯な気持ち、また内海校長と丹下先生の教育への熱意、KDDI様のプロジェクト推進のためのハードとソフトの両面での駆動力に背中を押され、多くのことを学ぶ機会に恵まれました。
芦生研究林は100周年を迎え、次の30年の目標として、「様々な生き物が棲む森へ 多様な人がともに学ぶ場へ」を掲げています。今回の取り組みは3者がそれぞれの得意な分野を活かし、ともに学び合いながら作り上げてきたものです。芦生研究林の森の課題解決だけでなく、地方や農山村、家族、人と人とのつながり、環境などを重視した持続的な社会の創出にむけた一歩となることを願っています。
このような大変素晴らしい成果をもたらしてくださいました、舞鶴工業高等専門学校の内海校長先生、丹下先生、HANDMADE部の学生の皆様、そしてKDDI株式会社様に、厚く御礼申し上げます。」
美山× 研究つながる集会は、大学等の研究成果を共有し、地域と研究者の新しい協働の取り組みが生まれることを目指す「地域と研究者の出会いの場」です。第3回集会は、特に大学教育と地域の関係をテーマに開催します。美山町では大学の学生実習やボランティアの受入が数多く行われてきました。実習では大学生が「茅葺き」「狩猟」「林業」「ガイドツアー」など様々な生業から多くを学んでいます。さらに実習を通じ、飲食や宿泊など地域経済にも寄与しています。またイベントや除雪などボランティアとして活躍してきました。
第3回集会では、こうした大学教育を、地域のラーニングツーリズムの発展や生業・暮らしの課題の解決につなげていくことを目指しています。大学や美山観光まちづくり協会の取り組みを紹介し、意見交換を行い、大学と地域による協働がさらに発展する「出会い」の場としたいと考えています。
日時:2023年2/28(火) 13:00~16:30
開催:京都丹波高原国定公園ビジターセンター 2階 セミナー室(定員50 名 先着申し込み順)+オンライン参加(ZOOM) いづれも参加無料
参加対象者:美山町住民、美山町の団体にご所属の方、美山町で研究している(研究しようと考えている)研究者・学生
申し込み方法:「会場参加」「オンラインでの参加」を希望される方は、右記QR コードを読み取り、申込フォームからお申込み。または、下記の申し込みフォームよりお申込み下さい。
「オンラインでの参加」申込みいただいた方には後日メールにて、Zoom のURL・参加方法等をご連絡いたします。
(ビジターセンター窓口でも受付しています)

13:45~「地域に通う、心が通う、課題解決型ラーニングツーリズム事業」 青田 真樹事務局次長
今年度美山町は、観光庁が進める「第2 のふるさとづくりプロジェクト」事業(「何度も地域に通う旅、帰る旅」という新たな旅のスタイルの普及・定着を図る国の施策)において、全国19 の実証地域の1つに選ばれ「地域に通う、心が通う、課題解決型ラーニングツーリズム事業」を実施しています。
特に、美山町においては大学生や企業を対象とした、地域住民との交流を伴う研修
プログラム実施による交流人口や関係人口の増加を図っています。
本発表ではその取組の一部を紹介します。
14:15~「人と自然のつながりを学ぶ森林フィールド」 石原 正恵准教授
芦生研究林は2015年に上賀茂試験地や北海道研究林とともに、文科省教育関係共同利用拠点「人と自然のつながりを
学ぶ森林フィールド教育共同利用拠点」として認定され、全国の大学や海外の大学の実習を多数受け入れています。本発
表では、こうした実習での地域との関わりと展望を紹介します。
14:30~「生物資源活用演習(三回生フィールド実習)を実施して:芦生研究林と美山からの学び」
前迫 ゆり教授
14:45~「美山町での実習の成果と今後への期待」 渡来 靖教授
2022年に美山町内で開催された大阪産業大学と立正大学の実習について、担当教員のお二人に、
実習を通じた学生の学びをご紹介いただきます。
15:10~意見交換「新たな可能性を探る」


10月22日(土)に京大ウィークス2022の一環として芦生研究林の一般公開を実施いたしました。当日は爽やかな秋晴れのなか、25名の方が参加されました。参加者の皆様には事前にお申込みいただいた希望ルートをもとに3班にわかれていただき、1,2班は原生林体験、3班は森林軌道としました。新型コロナウイルス感染症対策のため、1班あたりの人数を制限しました。原生林体験は大カツラと長治谷の間を1,2班の出発地点をずらして見学を行いました。原生林体験のコースはガイドツアー以外では一般入林することのできない、研究林内でも特に古くからの自然が残るエリアです。森林軌道コースは灰野集落跡までの道のりを往復しました。
両コースともに芦生研究林の教員と技術職員による生物や歴史文化の解説を交えつつ案内させていただき、終始和やかな雰囲気でした。構内に戻ってからは森林VR体験と、平日のみ開館している資料館を特別開放し、両体験を通じて芦生研究林の自然や歴史への理解を深めていただきました。どの企画でも皆様熱心にご質問頂き、この一般公開を通じて芦生の森をより身近に感じていただけたのではないのでしょうか。
今回の一般公開を機に、芦生研究林の森林や、森林で行われている様々な研究について一層のご興味をお持ちいただければと思います。
また今後とも芦生研究林の運営に、ご理解ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。




2022年9月26~28日(9月26日のみ芦生研究林、27,28日は上賀茂試験地において実施)
2022年度の森林利用学実習は、芦生研究林において2泊3日で行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため日帰りに変更して実施しました。参加した学生は19名でした。実習内容は美山町森林組合の間伐現場の見学と、芦生研究林内での防鹿柵等の見学でした。
午前中は美山町内の間伐現場にて、森林プランナーや現場班長に事業や現場の解説等をしていただきました。この現場の施業面積は約20haに対して山林所有者様が十数名いることから、集約化する際に苦労したお話や、利益還元のため所有者様ごとに椪を分ける必要がある(土場が多くなる)など、森林経営計画を策定する際の課題や、現場の課題を学ぶことができました。また実際の間伐作業の見学では、地際直径で1mはあろうかという杉の大木を伐っていただきました。美山町森林組合様のご協力により、充実した現場見学になりました。
午後からは研究林内に移動し、防鹿柵の見学と、石原林長と職員による芦生研究林の植生や歴史の解説を行いました。防鹿柵の有無により植生が目に見えて違うことや、種子の供給源が近くにないと植生の回復が難しいことなどを解説しました。また木地師の集団が生活していた名残が、山に生えている木によって伺い知れることなど、広い視点で山を観察できるようにという助言がありました。
実際に森林内を見学することで初めてわかる施業現場の声や、山の様子を肌で感じられたと思います。


2022年8月29日~8月31日に京都大学農学部の研究林実習Iが行われました。新型コロナウイルス感染症対策のため、1日1班(約15人)と人数を制限して日帰りで実施し、3日間で計47名の学生が参加しました。
今回の実習は下谷や幽仙谷近辺を中心に行いました。林道を歩きながら教職員が冷温帯の樹木解説を行いつつ、さく葉標本作成用サンプルを採取しました。
限られた時間の中での実習になってしまいましたが、京都市内とは異なる植生や、原生的な森林から、オンラインでは感じることができない多くの体験を得られたのではないでしょうか。


京都大学 大学院 農学研究科
森林科学専攻 森林利用学研究室
持留 匠
私たちは,森林とメタンについて調べています。
森林には様々な機能があります。例えば,木材を生産する機能,おいしい水や空気を作る機能,いろいろな動植物に住みかをあたえる機能などが挙げられます。なかでも,光合成によって二酸化炭素を吸収して木材として蓄積する機能は,地球温暖化を抑制するため重要だと考えられています。
しかし最近の研究で,木の幹からメタンガスが放出されている,という現象が報告されました。メタンも温室効果ガスですが,1分子あたりの温室効果は二酸化炭素の20倍ほど大きいと言われています。もし光合成による二酸化炭素の吸収量に匹敵するようなメタンの放出があったとしたら,これを見過ごすわけにはいきません。芦生の森でも,たくさんの樹種を対象に幹からのメタンの放出を測定することにしました。
昨年は,林内の13の樹種からの幹メタン放出を測定しました。メタンは酸素のない環境を好む古細菌によって,幹の中で作られている可能性があります。その場合,幹の直径が大きいほど活動が盛んだと考えられるため,特に大きな木を選んで対象にしました。13もの樹種の,それも大木と呼べるような木々を対象に研究ができるのは,古い森が多く残る芦生研究林ならではと言えるでしょう。
今年の測定では,手の届く高さだけでなく,高さ10mを超えるような幹の上部や,枝葉からのメタン放出も調べることにしました。そのために高所作業車をレンタルしたのですが,私たちは高所作業車を操縦する免許を持っていません。そこで,免許を持つ芦生研究林の技術職員さんに全面的にサポートしていただきました。高い技能や経験を持った職員さんがサポートしていただけるというのは,研究をするうえでとても心強いことです。お世話になった方々に,この場を借りてお礼を申し上げます。
これまでの測定によって,芦生での樹木からのメタン放出は光合成による二酸化炭素の吸収に比べれば,とても小さい量であることがわかってきました。また,放出に至るまでのプロセスや,場所や時間によって放出速度がどのようにばらつくか,ということも,少しずつ明らかにしている最中です。 これから収集したデータをまとめて,論文にして発表していきたいと考えています。これからも芦生研究林が森林研究の聖地として,充実した研究支援体制とともに脈々と受け継がれていくことを願っています。

