2019年9月18日から20日にかけて、有田川町立八幡中学校2年生4名の職業体験学習を受け入れました。
この学習は
・勤労の尊さや意義を理解し、望ましい職業観を養う。
・地域についての理解を深め、共によりよく生きていこうとする意欲を育てる。
・生き方についての自覚を持ち将来設計について考える機会とする。
といった目的で行われています。
初日は、研究林案内を含めた勤務場所の把握および環境省からの委託調査に関するリター回収、2日目は、立木の伐倒およびグラップル操作体験とその他重機操作体験を行い、最終日は、情報発信としてホームページ掲載原稿の作成と調査研究補助業務を行いました。今年度も神戸大学の佐藤准教授をはじめ、佐藤研究室所属の上田るいさん、田中良輔さん、田中達也さんに、調査研究補助業務として、体験学習の指導及び研究紹介をしていただきました。
以下、詳細はこちらに職業体験生に作成してもらったホームページ報告を記載しております。ご覧ください。
投稿者「waka」のアーカイブ
研究林内林道通行止めのお知らせ(追加)
令和元年7月24日より研究林内9林班、10林班において作業道の開設、立木の伐採が行われておりす。作業期間中、斜面上部から林道に伐採木、岩石の落下が予想されるため該当区域を通行止めとします。研究林事務所から茗荷平ゲートまでの通り抜けはできません。
上ウレビゲートより上部にて研究・調査をされる場合は事前にご相談いただきますようお願い申し上げます。
詳細はこちら *該当区域を変更しました(追記 令和元年10月24日)
また、7月12日に掲載しました通行止めのお知らせにつきましても引き続き通行止めとなっております。*災害復旧工事の完了に伴い、通行止めは解除しております。(追記 令和元年10月24日)
度重なる通行止めで皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
通行可能となりましたら、別途お知らせいたします。
よろしくお願いいたします。
入林制限解除のお知らせ
平成31年4月1日から令和元年7月22日にかけて行われた有害鳥獣捕獲のための入林制限について、捕獲期間を終了しましたので入林制限を解除しました。ご協力ありがとうございました。

和歌山研究林ミニ公開講座
和歌山研究林は和歌山県で最も標高の高い地域に位置する研究林です。このミニ公開講座では、モミやツガ、ブナの大径木が見られる天然林やスギを主体とする人工林をスタッフの解説により少人数で散策しながら、植物や森林の特徴について学びます。
- 日 程:
- 2019年10月19日(土) 9時30分~16時00分
- 会 場:
- 和歌山研究林(和歌山県有田郡有田川町上湯川76)
- 集合場所:
- 有田川町清水行政局前駐車場(有田川町清水387-1)
*JR藤並駅・阪和道有田ICから車で約50分 - 対 象:
- 斜面を歩行できる方。小学生以下は保護者同伴
- 定 員:
- 20名(応募者多数の場合は抽選)
- 参 加 費:
- 無料
- 持 ち 物:
- 弁当、水筒、山歩きに適した服装・履物、雨具
- 申込方法:
- 電子メール または 往復はがきかFAX(住所、氏名、フリガナ、生年月日、性別、昼間の連絡先(携帯電話・電子メール・FAXなど)を明記)
- *電子メールの場合、件名に【ミニ公開講座申込】と入力してください。
下記メールアドレスからのメールを受信できるように設定してください。
*FAXの場合、当研究林からの返信を必ず受信できる番号から送信してください。
*個人情報は本講座の運営以外には使用いたしません。 - 申込期間:
2019年7月29日(月) ~ 2019年9月9日(月)【必着】申し込み受付を終了しました。多数のご応募ありがとうございました。- 大変残念ながら悪天候のため、参加者の安全等考慮し中止とさせていただきます。多数のご応募ありがとうございました。
- 申込・問い合わせ先:
- 京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
電話 0737-25-1183 FAX 0737-25-0172
電子メール waka*kais.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)
*受付時間 8:30~17:00 (土日祝 8/13,14,休) - 注意事項:
- 悪天候の場合は現地の判断で中止することもあります。
イベント傷害保険に加入しますが(保険料は京都大学が負担)、加入保険の範囲を超える賠償の責任は、保障できません。予めご了承ください。
主催:京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
(京大ウィークス2019参加イベント)
後援:有田川町教育委員会
昨年の様子はこちら
通行止めのお知らせ
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林をご利用の皆様へ
*災害復旧工事の完了に伴い、下記該当区域の通行止めは解除しております。(追記 令和元年10月24日)
研究林内11林班の法面崩壊に対する復旧工事が7月13日から9月30日までの日程で行われます。工事期間中、該当区域が通行止めとなります。研究林事務所から茗荷平ゲートまでの通り抜けはできませんので、11林班丸太集積場より上部にて研究・調査をされる場合は林道清水笹の茶屋線へ迂回していただきますようお願い申し上げます。
皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
また、通行可能となりましたら、別途お知らせいたします。
よろしくお願いいたします。
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
県道19号(美里龍神線)通行止めのお知らせ(続報1)
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林をご利用の皆様へ
*災害復旧工事の完了にともない、下記区間の通行止めは解除されました(追記 令和元年10月24日)
5月8日付けのお知らせで掲載しました県道19号美里龍神線(清水橋から9kmほど先)、
法面崩壊箇所の災害復旧工事におきまして、清水方面より研究林へお越しの際は、林道
清水上湯川線のご利用をお願いしておりました。
前回お知らせ時に掲載した迂回路は幅員が狭いため、今回掲載します迂回路をご利用ください。
今回の迂回路を使用した場合、所要時間は50分程度です。
迂回路図に①から④までの交差点がありますが、わかりづらいため写真と説明を加えております。
お越しの際はこちらを参考にしてください。
何卒よろしくお願いいたします。
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
県道19号(美里龍神線)通行止めのお知らせ
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林をご利用の皆様へ
*災害復旧工事の完了にともない、下記区間の通行止めは解除されました(追記 令和元年10月24日)
昨年の台風20号による影響で法面崩壊していた県道19号美里龍神線(清水橋から9kmほど先)
において、法面崩壊箇所の災害復旧工事が行われます。
詳細は有田振興局からの災害復旧工事に伴う通行止めのお知らせをご確認ください。
工事期間中(5/8~8/27)は日曜・祝日以外9時から17時まで時間通行止めとなる
ため、清水方面より研究林へお越しの際は、迂回路として林道清水上湯川線の
ご利用をお願い致します。
工事の状況等変更がありましたら別途お知らせ致します。
何卒よろしくお願いいたします。
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
アマゴプロジェクト報告会について
2019年3月9日に有田川町きびドーム にて「有田川流域アマゴの健康診断プロジェクト」の報告会が開催されました。
このプロジェクトは、神戸大学大学院理学研究科の佐藤拓哉准教授らの研究グループと京都大学フィールド科学教育研究センターの徳地直子教授らが、地元や関西圏の釣り人の皆さんと共同で、有田川流域の在来アマゴを探し、その遺伝的多様性や周囲の環境状態を評価しようとするものです。
今回の報告会では、2018年に釣り人の皆さんが中心になって集めた約30河川のアマゴのサンプル(鰭の一部)をDNA分析した結果が紹介されました。今年も同様の調査とDNA分析を継続することで、有田川流域で昔から育まれてきた在来アマゴが見つかる可能性があるとのことです。
※このプロジェクトは、パタゴニアの環境活動研究助成と日本財団・京都大学森里海連環再生プログラムの助成事業として実施されています。

報告会の様子
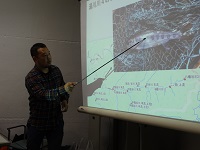
アマゴについての解説
入林制限のお知らせ
銃器によるニホンジカ等の捕獲を実施するため、下記のとおり入林を制限します。
|
実施期間 平成31年4月1日(月) から 平成31年7月22日(月) まで 入林禁止時間 平日(月~金) : 午前9時まで,午後5時以降 土日・祝日 : 終日 |
期間中は、平日は日出から午前9時まで、および午後5時から日没まで、土日・祝日は終日、林内で銃器を使用しますので、大変危険です。絶対に研究林内に立ち入らないで下さい。
なお、上記制限日時内での入林・利用を希望される場合は、個別にご相談ください。
この捕獲作業は、貴重な植生を守り、持続可能な森林管理を実現させるための活動です。ご理解とご協力をお願いいたします。
有田川町
和歌山県猟友会有田支部清水分会
京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
奨励賞の受賞について
和歌山研究林で研究を行っている神戸大学大学院理学研究科生物学専攻博士前期課程2年の上田るいさんが、日本生態学会近畿地区会例会(2018年12月2日(土)、於:京都⼤学フィールド科学教育研究センター)で奨励賞を受賞されました。
発表タイトルは「森と川の季節的つながりが維持するアマゴの生活史多様性」で和歌山研究林での野外操作実験を元に、森林から河川に流入する陸生昆虫の季節性が、サケ科魚類アマゴの生活史多様性の維持に寄与していることを明らかにされました。
今後も和歌山研究林を利用して研究される予定です。さらなる研究の発展と成果の向上を期待し、和歌山研究林としてもできる限りのサポートしていきます。

